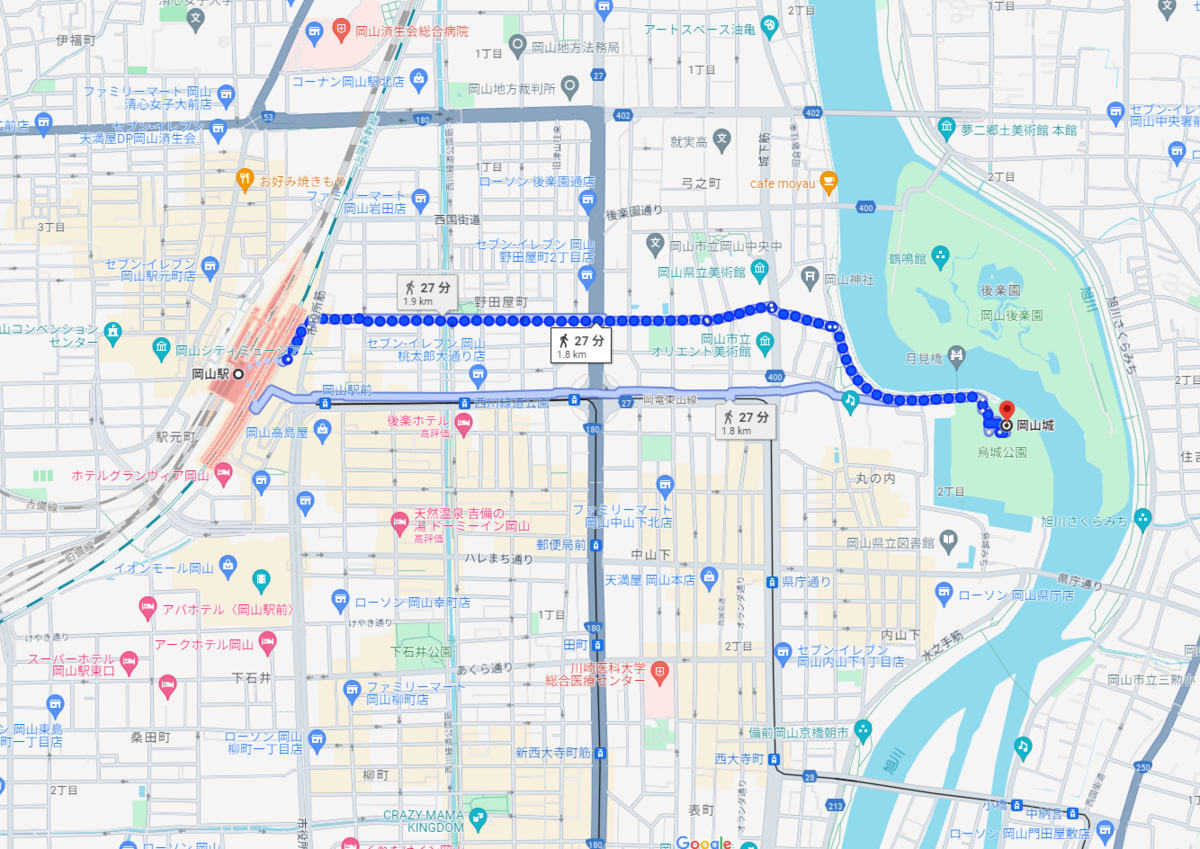江戸時代の弘前藩主は津軽氏である。移封されることもなく、江戸時代ずっと続いた。菩提寺もずっと弘前にあったが、戦国時代には藩主とともに移動している。その菩提寺は長勝寺である。
司馬遼太郎さんの『街道をゆく』の中の「北のまほろば」の中で、長勝寺とその周辺について、「いまの弘前の地に、高岡(鷹岡)という標高18メートルほどのひくい丘が隆起していた。[中略]。(この丘からは)津軽平野を一望に見ることができ、さらには天然の要害として岩木川がめぐり、西方と北方の備えをなしている。ただめざわりなのは、城の南に茂森という丘のあることだった。攻城する側がこれを奪えば、付城に使える。 「あれを平らに削れ」などと、津軽為信はいったはずである。げんに津軽為信が慶長12年(1607)、京で客死したあと、元和元年(1615)、茂森の丘はほとんど削られた。そのあとの西茂森に藩主の菩提寺長勝寺をはじめ多くの寺院が集中して置かれた。戦いのときは城方兵を籠めるのが、本来の目的だった」。
寺院の移動については長勝寺のホームページで確認できる。それを要約すると、次のような経緯を辿って弘前にきた。津軽家の祖・大浦盛信が父光信の菩提を弔うために、享禄元年(1528)に当時居城があった種里(現鰺ヶ沢町)に、長勝寺は建立された。その後、大浦(現弘前市五代、旧中津軽郡岩木町)を経て堀越(弘前市堀越)へと、津軽氏の本拠地の移転とともに移り、慶長16年(1611)に、弘前藩2代藩主津軽信枚が弘前に居城を移すとともに現在地に移った。
さらに同じホームページによれば、曹洞宗の長勝寺移転とともに、領内の曹洞宗寺院33寺が、同じ場所に集められ、寺院街を構成した。弘前城を防衛するための前線基地のような軍事的性格を持ち、現在も残る土塁を含め長勝寺構(がまえ)と呼ばれている。江戸時代初期での同一宗派33寺による寺院街建設は全国でも例がないとされている。一直線の禅林街の一番奥、突き当りに位置するのが長勝寺である。
グーグルマップからはその様子が分かる。写真で手前(南)が長勝寺、まっすぐに上の方に延びる道路に沿って寺院が並び、禅林街をなしている。

禅林街の一番奥にある長勝寺を参詣するためには黒門を抜ける。案内板には次のように説明されている。黒門は外枡形、土居、濠跡及び曹洞宗寺院群とともに史跡弘前城跡長勝寺構を構成する重要な遺構の一つで、長勝寺三門杉並木等とあいまって西茂森禅林街の歴史的好環境をつくりだしている。現位置における記録上の所見は貞享4年(1687)作成「長勝寺耕春院惣構」の図に見られ、黒門は長勝寺境内入口を示す総門(表門)としての機能を有していた。この門が城郭建築にみられる高麗門形式となっているのは長勝寺一帯が弘前城の出城として性格付けられていたことによる。弘前城にない高麗門形式が出城としても長勝寺構に現存することは興味深いことであるが、建造当初からの形式によったかどうかは定かでない。

黒門を抜けて、禅林街を歩いていくとは先の方に長勝寺が見えてくる。

振り返るとスタート地点の黒門が見える。

それでは長勝寺の説明に移ろう。境内の案内文によれば、三門・銅鐘・本堂・庫裏が国指定重要文化財に指定されている。そしてそれぞれは次のように説明されていた。
三門:嘉永6年(1629)、2代藩主信牧により建立された。この後数回の改造を経て、文化6年(1810)には火燈窓を設けるなど、ほぼ現在の形となった。上下層とも桁行9.7m、梁間5.8mで棟高は16.2mである。組み物は三手先詰組とし上層縁廻の勾欄親柱に逆蓮柱を用いるなど、禅宗様の手法を基本としている。また、柱はすべて上から下までの通し柱で、特殊な構造となっている楼門である。

銅鐘:鐘は、嘉元4年(1306)の記年銘があるところから嘉元の鐘と呼ばれている。寄進者の筆頭に鎌倉幕府執権・北条貞時の法名があり、さらに津軽曽我氏の棟梁や安藤一族と考えられる名前なども陰刻されている。中世の文献がほとんどない当地において、北条氏と津軽の関係を示す貴重な資料である。

本堂:慶弔5年(1610)に造営されたと伝えられている。桁行22.7m、梁間16.3m、入母屋造。折桟唐戸を吊り、上に筬(おさ)欄間を設けている。部屋は8室構成とし、間切りは1間毎に角柱を立て2本溝の仕切りを置く。仏間は板敷きとし、正面中央に円柱を立て、左右の脇間には菱欄間を設けている。古い形式を随所に遺し、津軽氏菩提寺の本堂として記念すべき遺構である。

庫裏:桁行18.1m、梁間13.9m、屋根は切妻造で茅葺、大浦城台所(文亀2年(1502)建築)を移築したと伝えられ、各柱に登梁を架け渡し、これに小屋束を立てて和小屋を構成する。一部改造個所もあるが、当初の姿で保存され、中世にまで遡り得る構造形式を残している遺構として貴重である。

内部

庫裏の反対側には、五百羅漢が安置されている蒼龍窟(そうりゅうくつ)がある。

そして蒼龍窟の入口には厨子堂がある。長勝寺のホームページによれば、大型の1間厨子で、入母屋造の木瓦葺。百沢寺の本尊を祭るために1638(寛永15)年に3代藩主信義が造営した建物で、もともとは現在の岩木山神社拝殿内部に設置していた。明治時代の神仏分離令により百澤寺(ひゃくたくじ)が廃寺となり、長勝寺に移築。三尊仏は、津軽為信が慶長8(1603)年に岩木山百沢寺大堂の本尊として祭ったものと伝えられ、三体とも寄木造り、胡粉箔仕上げの桃山時代の作とみられる。

境内の右奥には、津軽氏の墓所がある。御影堂は国指定重要文化財である。弘前市のホームページには次のように説明されている。御影堂は初代藩主為信の木像(県重宝)を祀った堂で、内部の厨子と須弥壇は重要美術品に認定されていた。創建は三門と同じ寛永6年(1629)と伝えられ、文化2年(1805)に正面を南から東に改め、全面的な彩色工事が実施されたという。方3間、屋根を宝形造の銅板葺とし、軒は二軒疎(ふたのきまばら)垂木である。四周中央間には、内側に草花図柄を密陀絵で描いた黒漆塗の桟唐戸がついている。内部の架構は虹梁を主体とし、来迎柱や天井などには極彩色で絵や文様が描かれている。厨子も極彩色で、各部に金箔や金泥が多用され豪華である。この建物は、南に配された津軽家霊屋と一体となった藩祖を祀る御影堂として貴重である。
中央が御影堂。

霊屋は国指定重要文化財である。案内板によれば、霊屋は御影堂より南へほぼ一線に並び、環月臺(初代藩主為信室霊屋・寛文12年(1672)造)、碧巌臺(2代藩主信枚霊屋・寛永8年(1631)頃造)、明鏡臺(2代藩主信枚室霊屋・寛永15年(1638)頃造)、白雲臺(3代藩主信義霊屋・明暦2年(1656)造)、凌雲臺(6代藩主信著霊屋・宝暦3年(1753)造)である。5棟とも方2間、入母屋造、こけら葺で妻入である。また正面は桟唐戸、他は板壁で、各棟各面とも外面に津軽家家紋の杏葉牡丹が描かれているが2代信枚室の満天姫が徳川家康の養女であったことから、明鏡臺の各面は葵の紋で飾られている。内部には石造無縫塔が安置され、壁に板卒塔婆が張り巡らされているほか、鏡天井には白雲臺に天女、他の四棟に龍の絵が描かれている。いずれも江戸時代前期から中期に属するもので、本格的造りになる霊屋が建ち並ぶ景観は優れており、年代の明らかな近世の霊屋群として重要である。
左から右へ、碧巌臺、環月臺。

左から右へ、白雲臺、明鏡臺、碧巌臺。

左から右へ、明鏡臺、碧巌臺。

長勝寺の説明はここまでである。古風で威厳のある三門に圧倒されたが、境内は通常の寺院とは趣が異なり、武士の館を連想させるような本堂と庫裏には、宗教的な雰囲気が感じられず、戦国時代に戻ったような異様さの中に吸い込まれた。次回は、寺町の雰囲気が漂う禅林街を説明する。