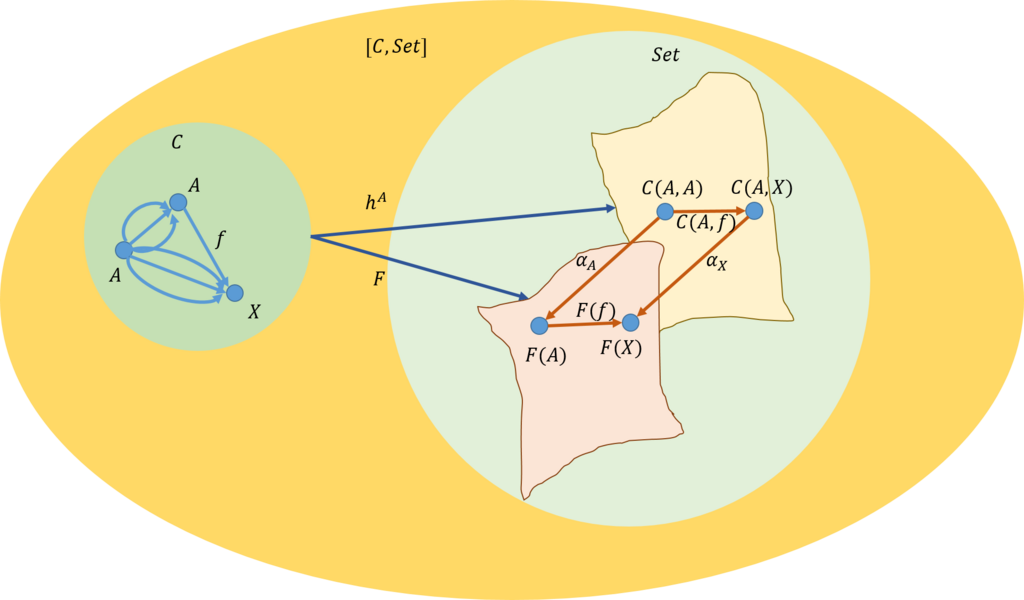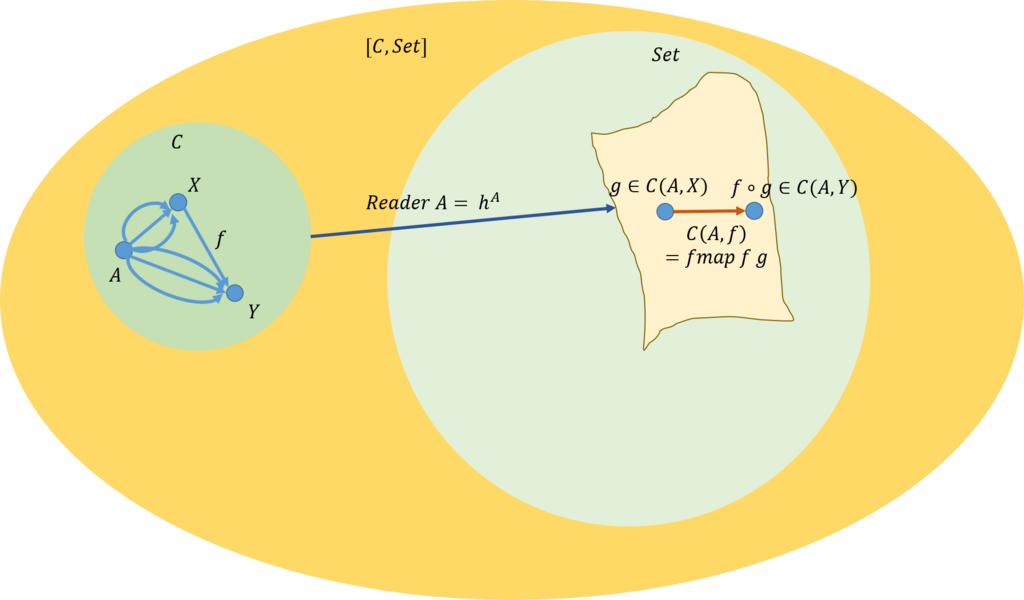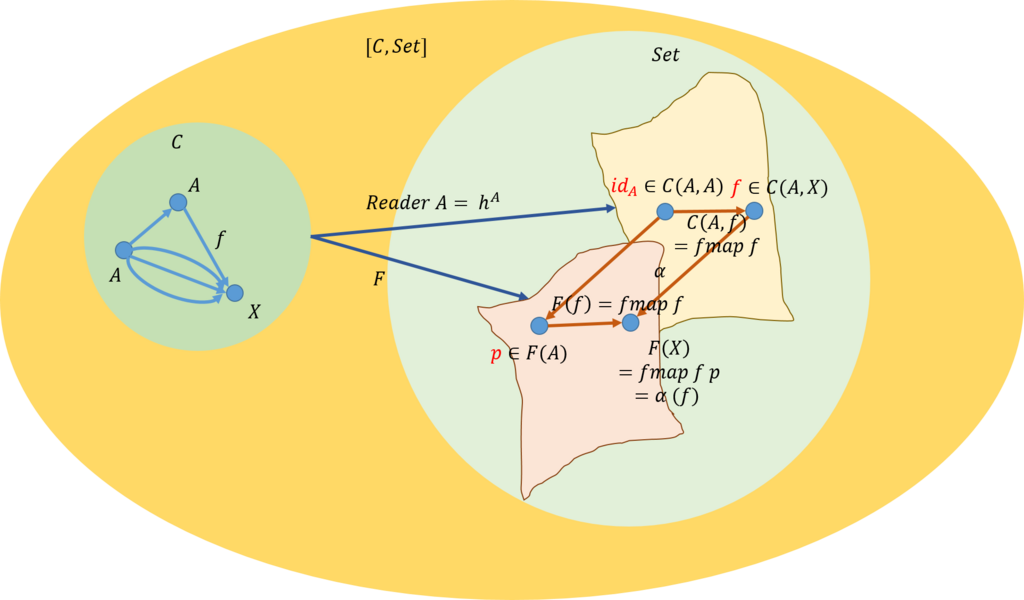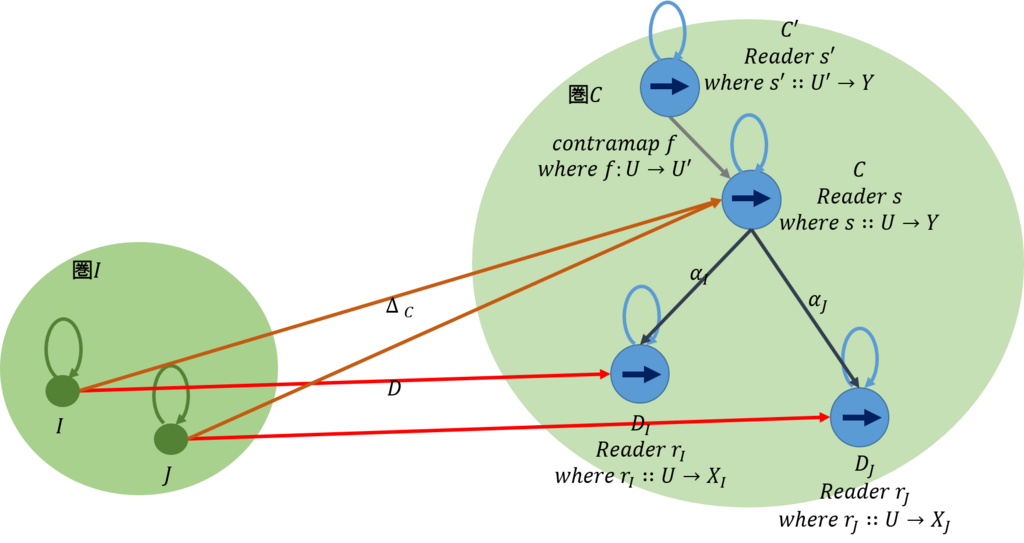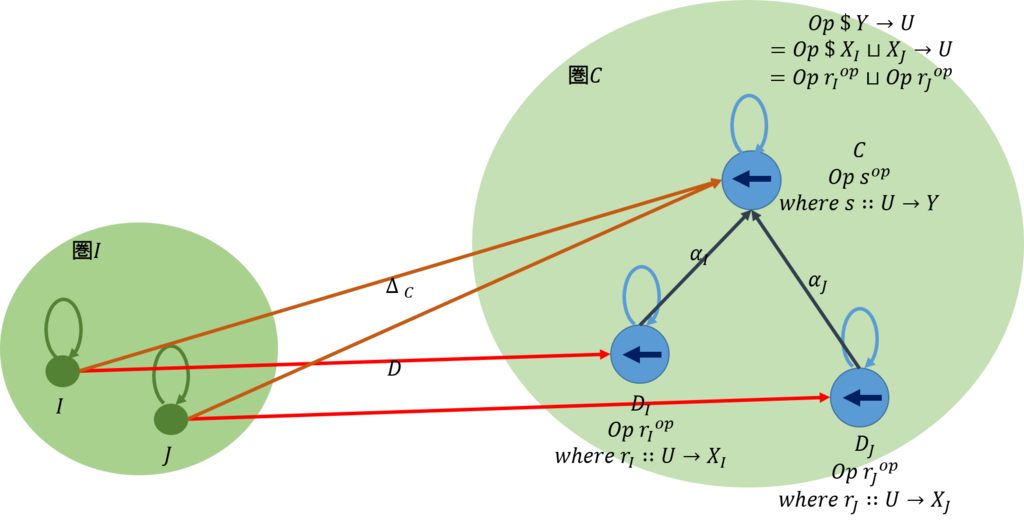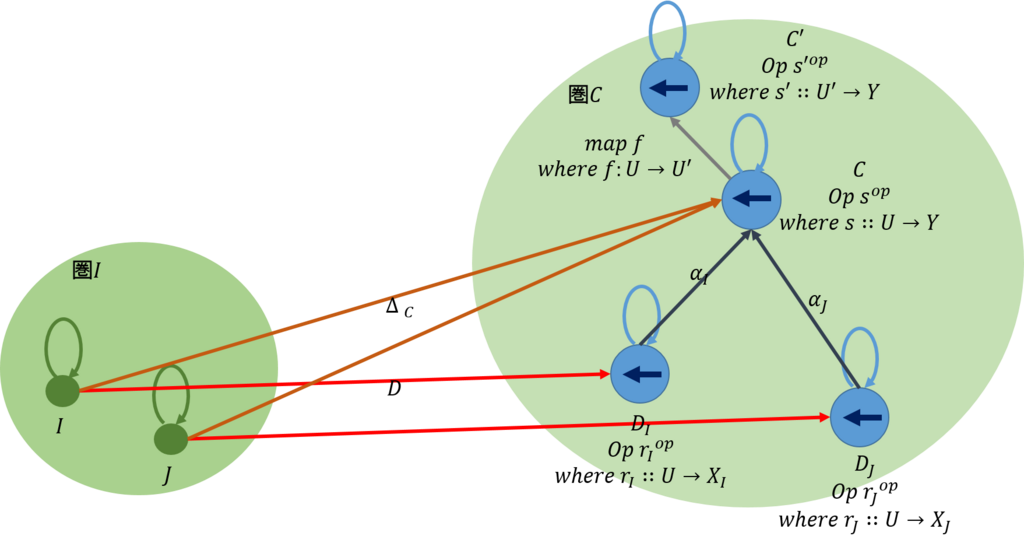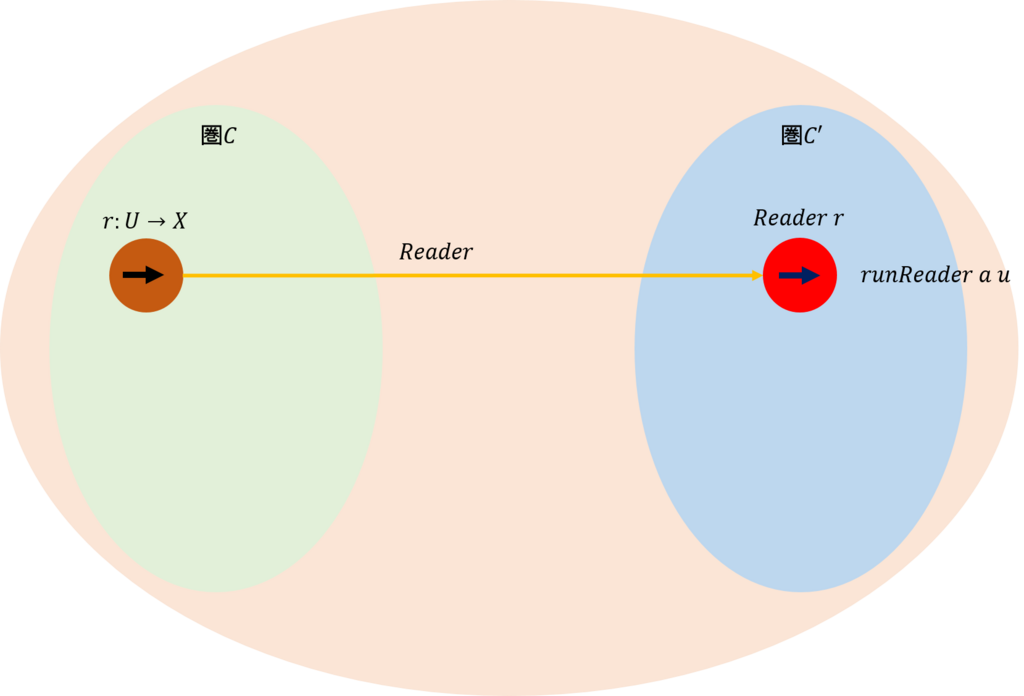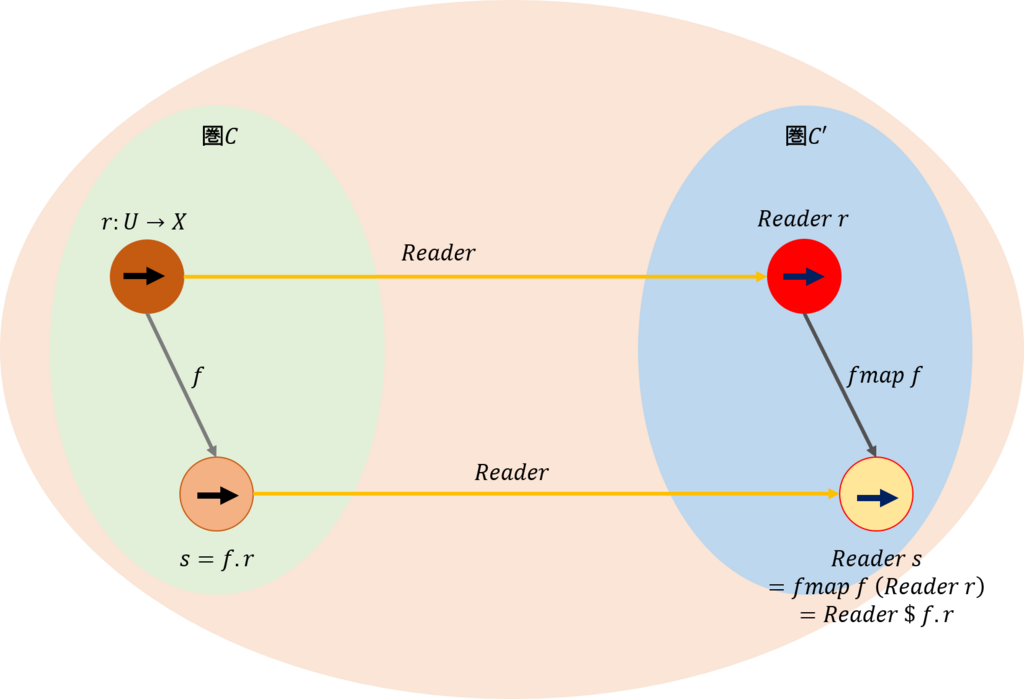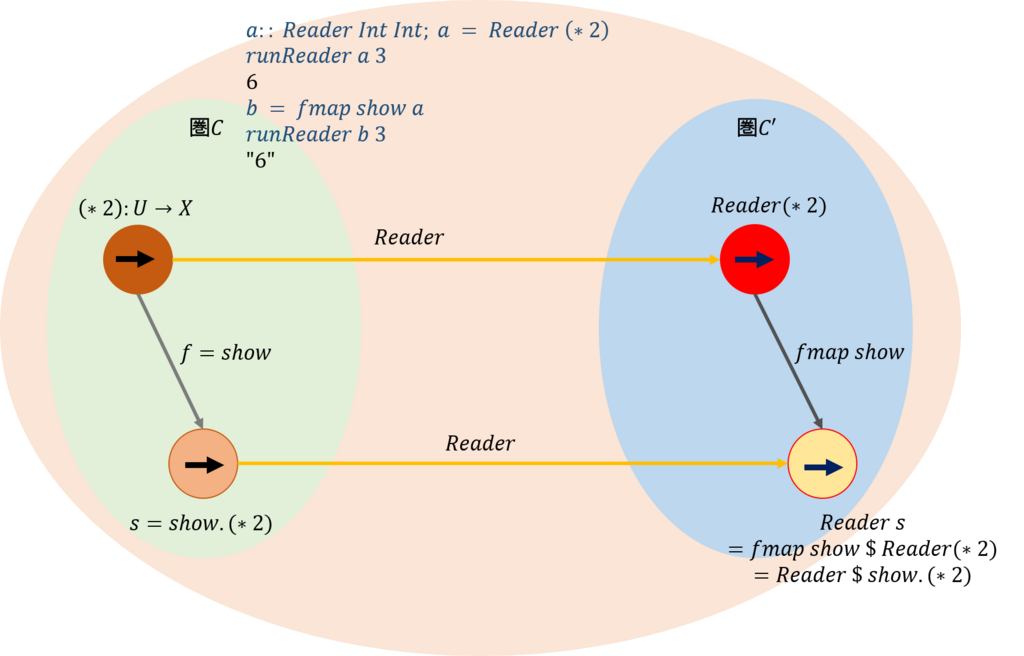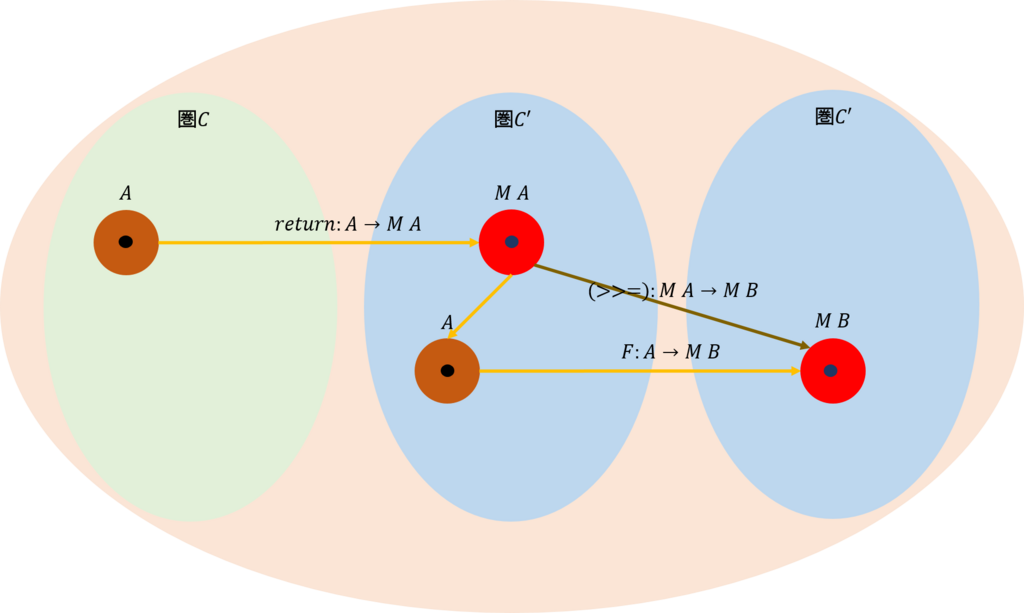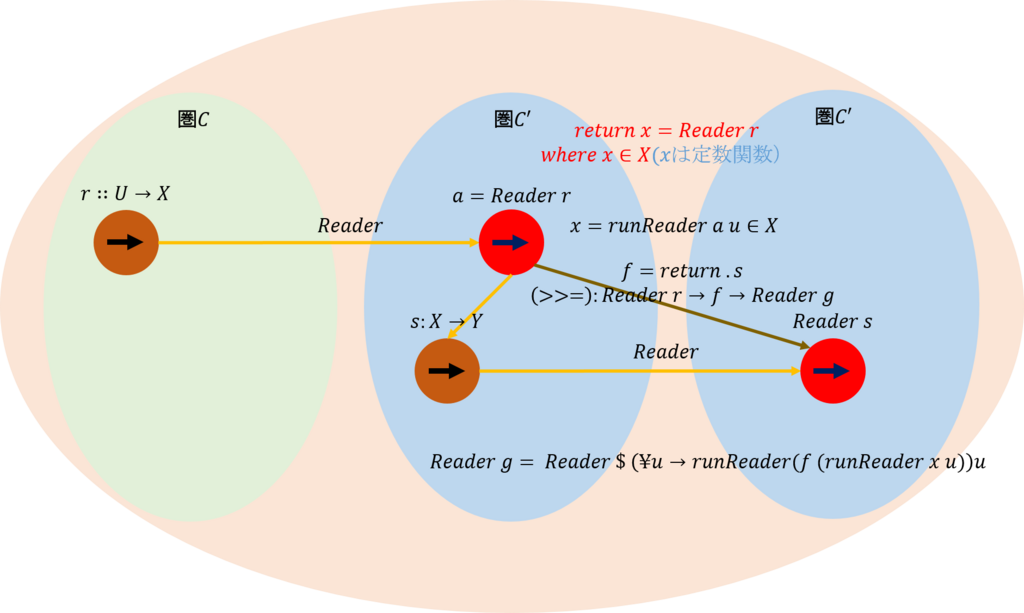お医者さんに「成長させ過ぎですね」と言われた背中のこぶを取ることになった。あの事件が起きなければ、いまだに、こぶが自己顕示欲を高めながら、息づいていたかと思うと、なくなってしまった今となっては哀れにさえ思える。
事件は突然起こった。昨年の秋は雨の多い日が続いたが、そのようなある日、冷蔵庫の中が寂しくなってきたので、近くのスーパーに買い物に出かけた。野菜や果物や肉を満載したカートを押しながら屋上の駐車場に出ようとしたときだった。運の悪いことに、駐車場への出口はスロープになっていて、表面は雨で濡れていた。
スロープに2,3歩踏み出したとき、両足のテニス靴がゆっくりと滑り始めた。体を支えようとしてカートに体重を移した瞬間に、カートが勢いよく逃げていった。あっという間の出来事なのだが、転んでいくなか、スローモーションのようにコントロールのできない体の動きを体験する。テニス靴がスピードにのって前にどんどん滑っていく。腰が後方に取り残され、お尻がまっすぐにすとんと落ちていく。一生懸命に体を支えようとした左の肘を、したたかにコンクリートに打ち付けつけてしまった。
後ろにいたおじさんに、「大丈夫ですか」と心配される。強がって、「大丈夫です」といったものの、かなり強く打ったようで、痛みは激しい。手を動かすことはできたので、たいしたことではないだろうと高をくくっていた。
このような事件があったことも忘れていた2か月後に、湯船につかって、肘をお風呂の側面に押し付けたとき、感覚がないことに気が付いた。触ってみると、肘に大きなこぶができている。柔らかいこぶで、手で押すと移動する。転んだことが原因なのだろうかと思い、定期検査の時に知り合いの医者に相談したら、整形外科で見てもらってはというアドバイスを受けた。
毎年、近くの病院でインフルエンザの予防接種を受けているが、都合のよいことに、その病院のお嫁さんが、独立して新たに整形外科の病院を開院したので、早速、そこで、診察を受けることにした。開業二日目で、ほかに患者もおらず、丁寧に時間をかけて診察していただいた。肘のこぶを見た瞬間、看護婦さんと顔を見合わせて、嬉しそうに「滑液包炎ね」と言われた。通常は、滑液包の中に少量の液体が入っていて、クッションの役割をしているのだが、転んだことで炎症を起こし、滑液が余分にたまっているということで、注射針を刺して抜いてもらった。
そして、もう一つこぶがあるので診てくださいとお願いしたところ、「二つもこぶのある人は珍しい」と言いながら、背中に目をやった瞬間、「こちらの方は大変」と言われた。5cmを超えると「生検」が必要とも言われた。とりあえず、エコーで調べてみようということになったが、大きすぎて全体が写らないとのこと。「ずいぶん大きい」と言われた。大きな病院で、「MRIを撮ってもらい、それで判断しよう」ということになった。
紹介された病院でMRI検査を受けた。MRI検査の技師の人からも「大きいですね」と言われる。そして、MRI装置のベッドにうつ伏せに寝てくださいと指示される。顔の部分にタオルを敷いてもらい、顔を横向けにする。すごい音がするということで、耳栓をする。撮影には30分程度かかったが、顔を横に向けていたため首が痛くなり、往生した。技師の人によると、「おそらく脂肪腫でしょう」ということだった。ただ、通常は、一つの袋の中に脂肪が収まっているが、いくつもの袋があるようだといって、画像を見せてくれた。綺麗に撮れるものだなあと感心しながら、CDに画像をコピーしてもらった。
整形外科医に戻って、MRIの検査結果を診断してもらった。脂肪腫ということだった。脂肪腫は、よくみられる病気の一つのようで、妻の知り合いの中には手術を受けた人が少なからずいた。文字通り、脂肪の塊が体の中にできるのだが、その原因は不明だそうだ。5cm以下の大きさなら様子を見ることになるそうだが、残念ながらその大きさをはるかに超えて、直径9㎝、厚さ3㎝であった。手術をし、さらに、生検した方がよいとのことだった。この病院では手術はできないので、大きな病院を紹介するということなので、お願いした。
年が明けて、紹介してもらった病院を訪れた。ここのお医者さんにも、見た瞬間に、「大きいですね。成長させ過ぎましたね」と言われた。そして、「ここまで大きいと、麻酔も多く使うし、大きな空間ができるので溜まった血液を抜くためのドレーンも必要になります」と言われた。手術は、1時間程度、日帰りで大丈夫ですということなので、お願いした。
手術前の検査が必要ということで、尿検査、血液検査、レントゲン検査を受けた。医療者の安全を守るために、HIV検査、肝炎検査が含まれていた。
1週間後の手術ということだったが、運悪く、風邪をひいてしまった。予定していた手術の前日に病院に相談したら、「風邪が完全に治ってから改めて手術日を決めましょう」ということになった。
再度仕切り直して、1月30日に手術することになった。手術の当日、1階の処置室で手術着に着替え、看護婦さんに案内されて、2階の手術室に向かった。手術には、診察してくれた主治医の先生のほかに、若いお医者さんが一人加わっていた。看護婦さんは2人だ。
MRI検査での嫌な記憶が残っていたため、うつ伏せに寝ることに抵抗があったが、今回は、苦しくならないように配慮されていた。胸のところに小さなウォータベッドのようなものが置いてあり、上半身を支えられるようになっていた。これで、頭を横に向けなくても済むと思って安心した。顔が当たる部分には、タオルが置かれていたが、タオルを追加してもらい、顔が快適な位置にくるように調節した。
ベッドに横たわると、左腕の血管には点滴用の針が刺され、指には脈拍数・酸素測定のための、右腕には血圧計のための器具が装着され、また左の太ももに電気メスの対極板が貼られた。
背中の部分だけを出して、他の部分は大きなシーツで覆われた。このため、シーツの中に顔が埋まってしまい、周りは全く見えない。看護婦さんが、シーツをめくり、声をかけてくれるときだけ、孤独感から解放されるという状態に置かれた。
準備の間、二人のお医者さんが相談している。「これは大きい」と言っている。こういう時のお医者さんの心境はどのようなものなのだろう。複雑な手術で嫌だなあと感じているのだろうか、それとも、普段できないことに挑戦する機会を得て、うれしいと思っているのだろうか。私なら絶対に後者だが、お医者さんもそうであってくれればと願っているうちに、「タイムアウトです。それでは始めましょう」と掛け声がかかった。手術の時の決まりなのだろう、「大きい脂肪腫の除去。氏名はXXさん。年齢はX」と言っていよいよ始まった。
局部麻酔なので、背中の数か所に麻酔が注射される。針が入っていくときの痛みはあるが、たいしたことはない。手術を受けるにあたって、MRIの画像をパソコンであらかじめ詳細に見て、素人なりに手術の手順を想定してきたので、お医者さんの会話や背中からの刺激をもとに、進行状況を想像した。
最初は、皮膚の部分を切っているのだろう。少し、焦げたような臭いがした。手術の前に、「痛みを感じたら言ってください。麻酔を足しますから。我慢して、急に飛び上がられても危険ですから、お願いします」と言われていた。切り始めて、すぐに痛みを感じ始めたので、「痛いです」と言うと、麻酔を足しますといって処置してくれた。
脂肪腫の取り出しが始まったのだろう。右上の方を切断しているようだ。何かで引っ張っているのだろうか抵抗感がある。そうこうするうちに、電気メスで切り始めたのだろうか、痛みを感じる。この痛み、何とも不思議だ。今までは感じたことがないような痛みだ。それほど強いわけではない。何か、びりびりとくるような気持のよくない痛みだ。我慢できそうなのだが、手術前に言われているので、痛いことを何度となく告げた。
この部分が終了し、他の部分を処置した後、下側の切除が始まった。同じような痛みを感じる。同じ痛さなのだが、痛みは長いこと継続していると、耐えることが苦痛になってくる。「痛い」と連発する。麻酔を足しても、痛いというので、若いお医者さんが疑問に思ったようだ。「どこら辺が痛いですか」と質問してくる。「背中の下の方です」と答えると、主治医の先生が、「複雑な部分を切除しています。全部、取りきらないと再発する恐れがあります。もう少しで終了しますので、頑張ってください」という。難しい部分だったのだろう、若いお医者さんが「先生、お見事ですね」と言う。うまくいったのだろう。主治医の先生が、「気をつけないとこの部分は穴をあけてしまうよ」と言っている。主治医の先生はきっと上手な外科医なのだろうと安心した。
他の部分の切除が始まった。軽やかに切れていくような感触が伝わってくる。安心して、静かにしていると、お医者さんの方が心配になったのだろう。「XXさん、大丈夫ですか」と確認に来る。「大丈夫です」と元気に応えて、お医者さんに不要な心配をかけないようにする。でも、緊張が続いたせいか、右側のこめかみの血管のあたりで頭痛を感じるようになる。血圧が高くなっているためかなと思って、気を静めるように心がける。あまりに静かにしていたためか、お医者さんから再度確認が入る。同じように、元気に「大丈夫です」と答える。その後も何回かは痛い時があったので、時々は痛いですと訴えた。そうこうするうちに、「もう少しで終わりです。止めてくれと言われても、もうダメです。もう少し頑張りましょう」と言われた後は、静かに終了するのを待った。
看護婦さんがシーツをあげて、「切り口をきれいに縫っていただいて、終わりになります」と教えてくれた。やっと、終わりかとほっとする。お医者さんの方は、「きれいにと注文されたので、心して綺麗に縫わなければ」と冗談を飛ばしながら、作業をしてくれた。その間、縫合に使われる糸の特徴についてお医者さんの間で意見を交わしていた。ゆるみやすい糸があるなどと言っていたが、今回はどのような糸を選んでくれたのだろうか。
最後に、脂肪腫除去後の空間に溜まる血液を排出するためのドレーンがつけられ、手術は無事、終了した。
看護婦さんの話では、電気メスによる痛みは広い範囲に及ぶので、麻酔の効いていない離れた部分で痛みを感じるのだろうと言っていた。「我慢すればよかったのですが、なかなかね」と看護婦さんに言うと、「我慢しなくてよかったのですよ」と言われた。麻酔は39cc使ったそうだ。あらかじめ40ccを用意したとのこと。この量が限度なのだろう。配分を考えながら、麻酔を打ったものと思われる。このため、痛いといったとき、麻酔が足されないことも多かったのではないかと推察した。
ドレーンは、切開場所ではなく少し離れたところに、差し込まれている。そこに細い管が繋がっていて、その先には、液を溜める容器が接続されている。血液はスポイトと同じ原理を用いて自然と抜かれる。液を溜める容器は弾力性があり、容器に取り付けられている栓を外し、容器を押してペチャンコにすると中の空気が抜ける。この状態で、栓をすると容器の中が減圧された状態となるので、ドレーンの管を通して手術跡に溜まった血液を容器に排出できる。簡単な装置なのだが、何とも、よくできている。ドレーンは4日後に取り外しましょうとなった。
お風呂は足浴ならぬ下半身浴ならばよいとのこと、シャワーは浴びてもよいとのことだったが、傷口が濡れるのが嫌だったので、シャワーの方はしばらく我慢することとした。2月10日に生検の結果が分かる。良い結果であることを期待している(検査結果はただの脂肪腫だった。一安心した)。
複雑な手術を手際よくこなし、順調に痛みもなく回復してゆく状況に接するとき、プロとしては当たり前のことなのだろうが、お医者さんはすごいなあと改めて感じて、感謝の気持ちでいっぱいになった。