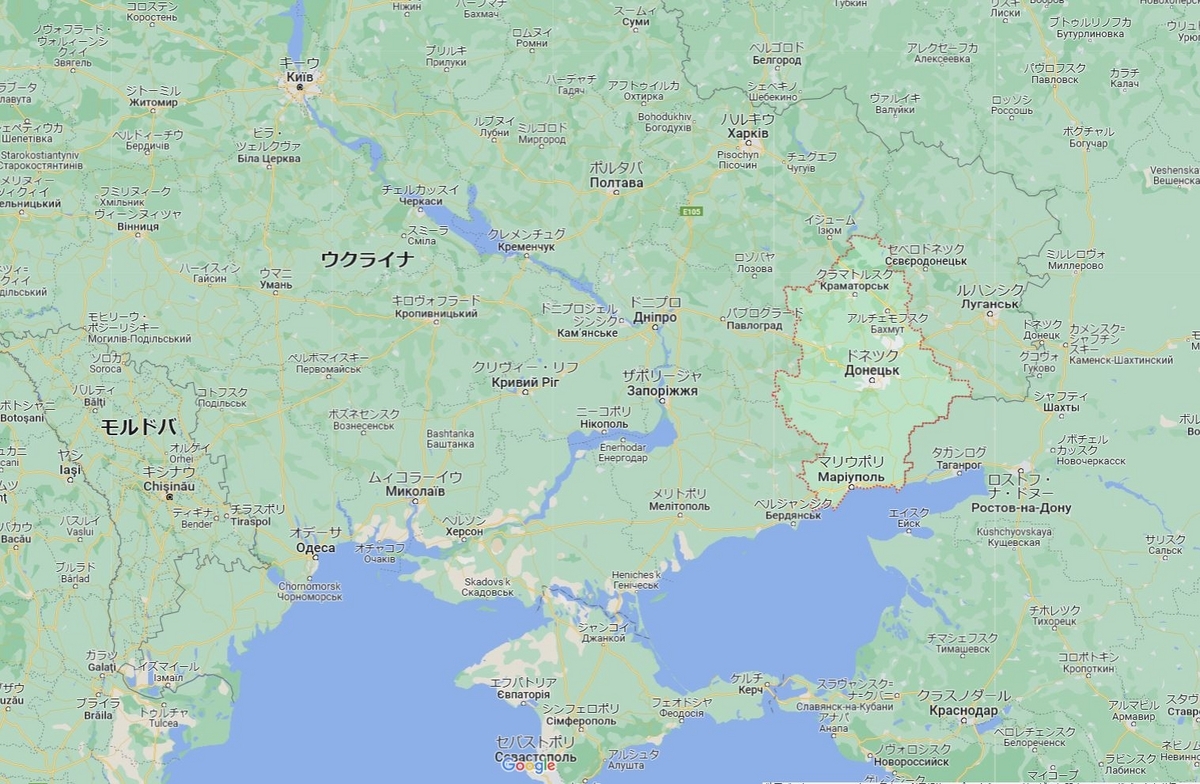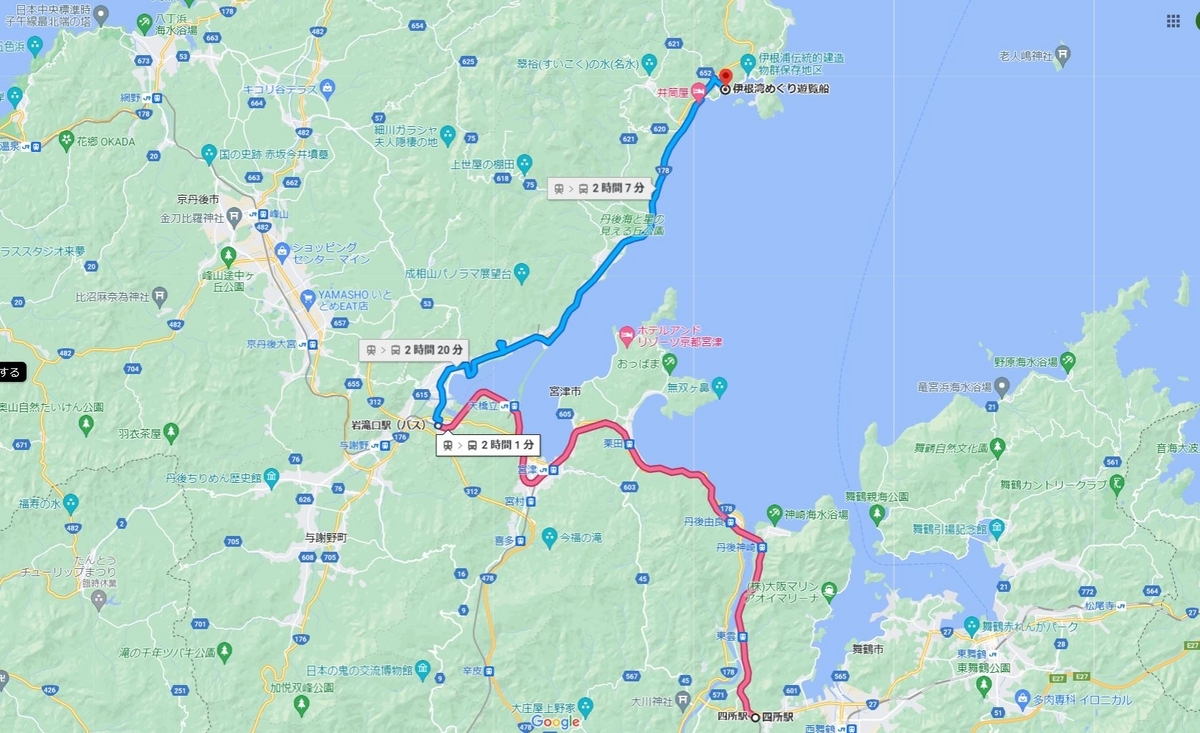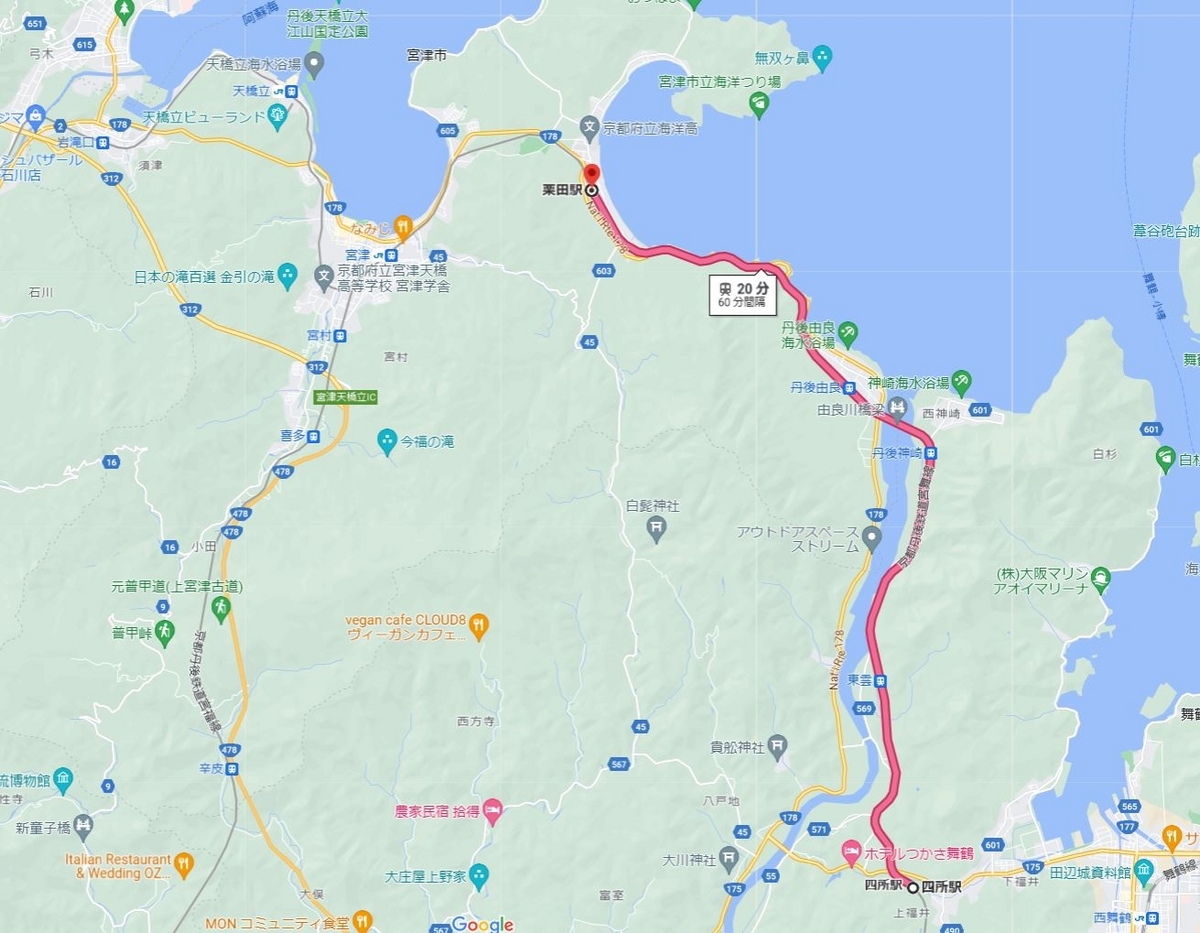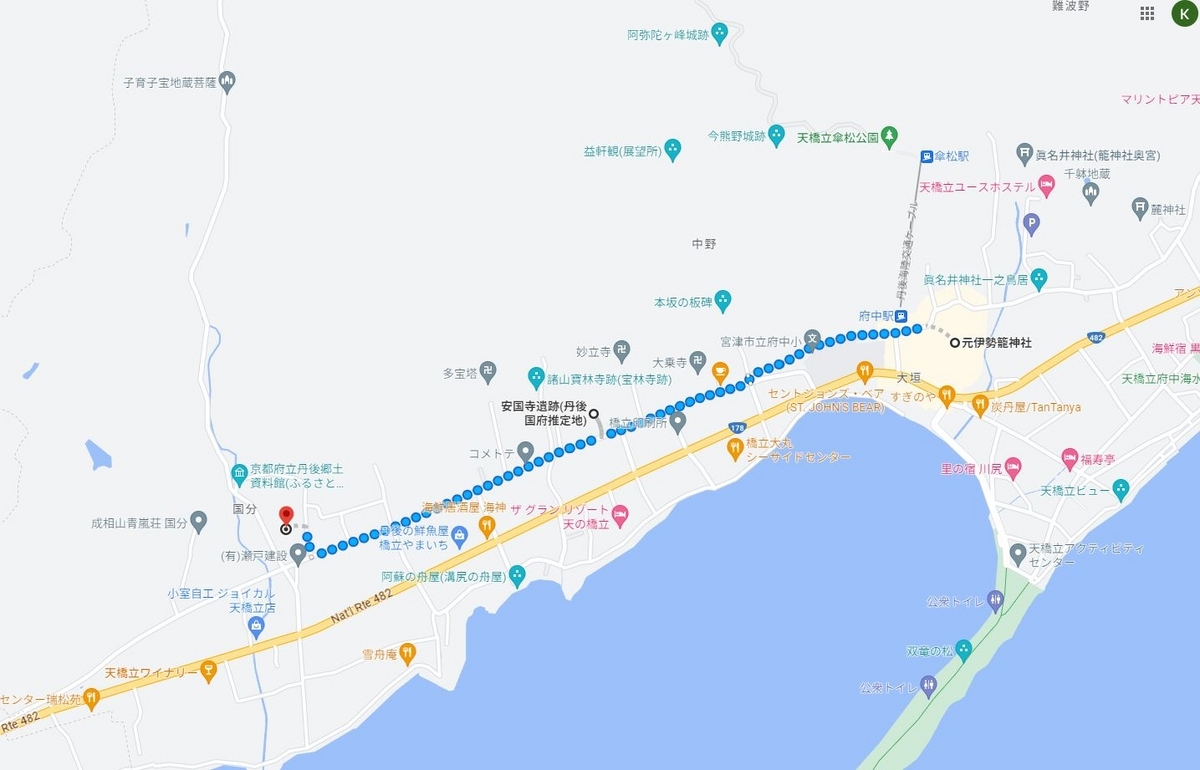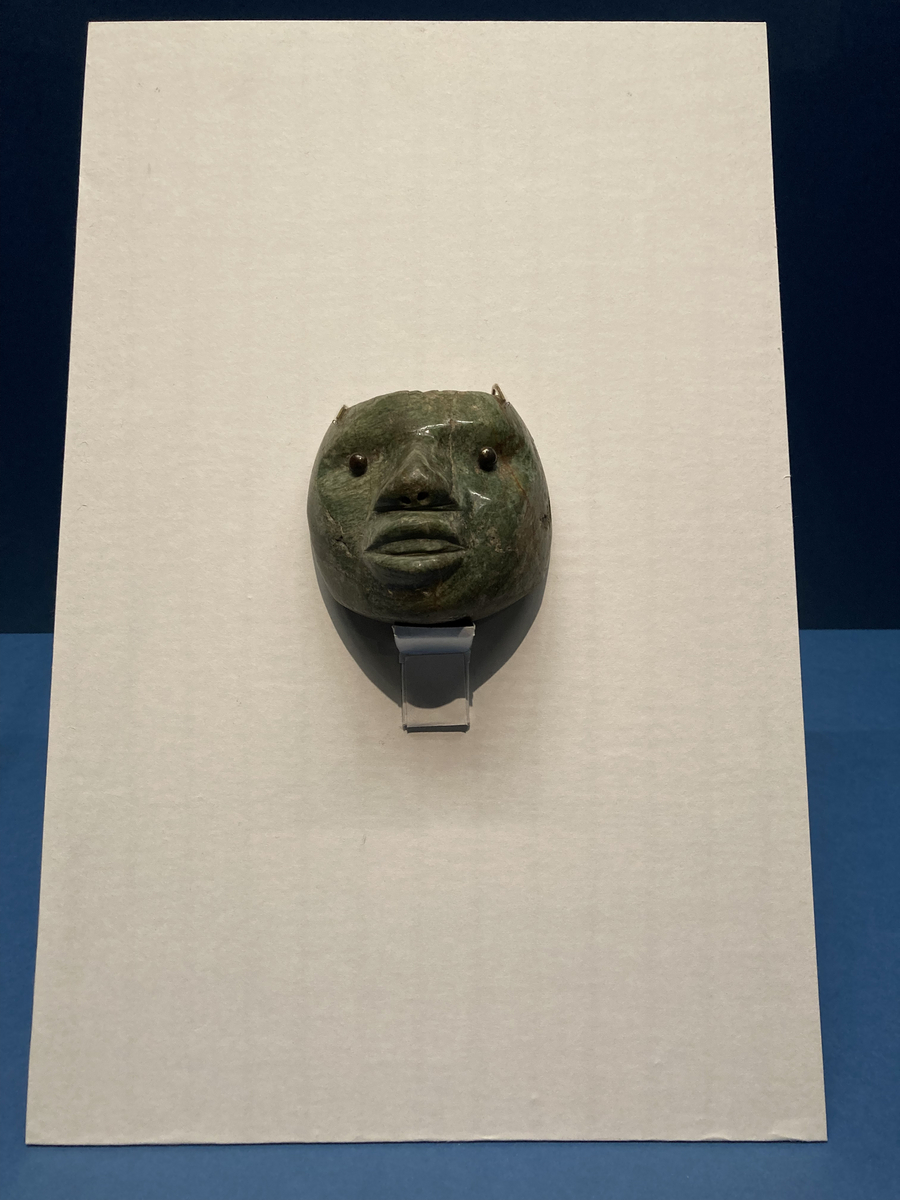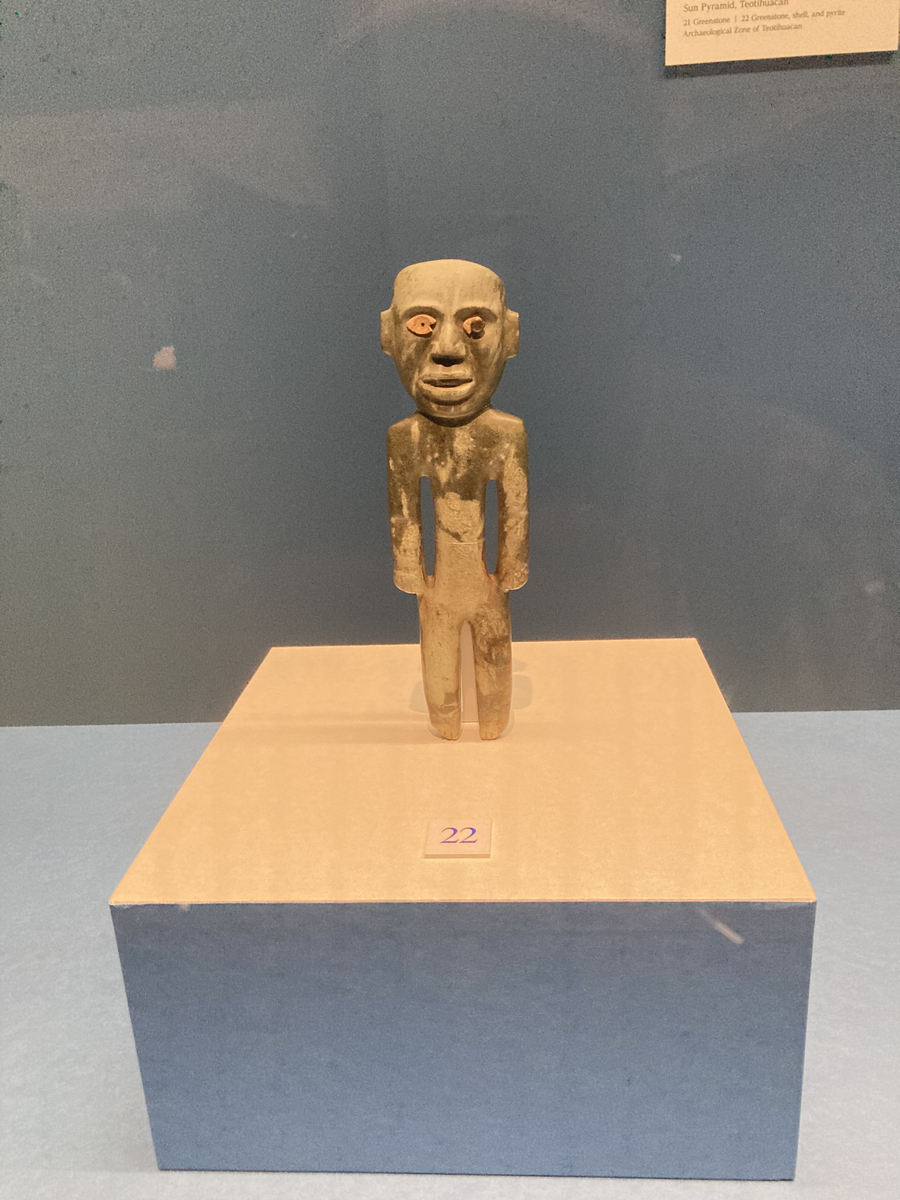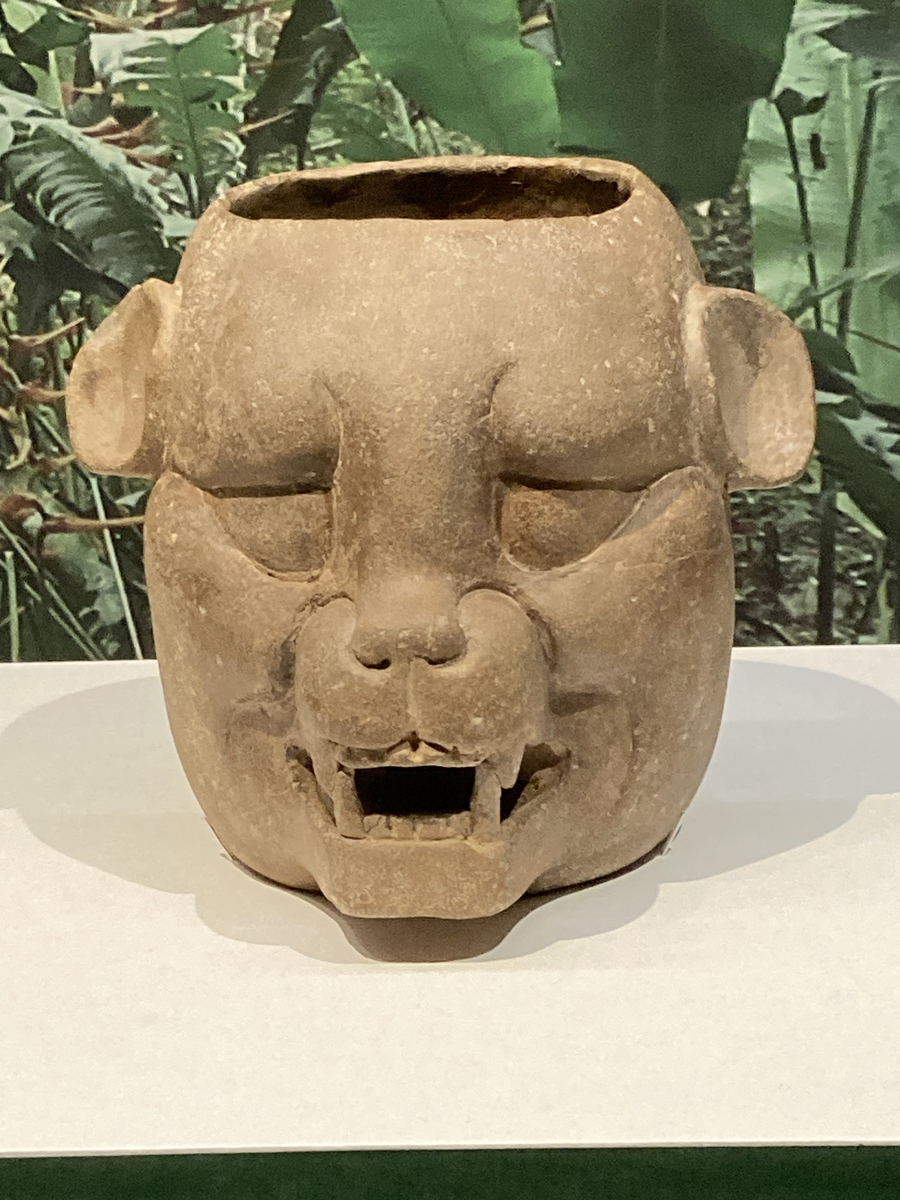博物館を訪問する機会が増えるにしたがって、仏像を見る機会も多くなってきた。しかしそれぞれの歴史や意義を問われると答えに窮してしまうことのほうが多い。どうも仏教に関しての知識が頭の中で整理されていないことが原因のようだ。そこで手抜きをして重要なポイントだけを得ようと思いこのテキストを熟読した。
NHK Eテレの「100分de名著」はもう10年以上も続く教養番組で、世間で名著とされている本をその分野の専門家を招いて25分ずつの4回で分かりやすく説明してくれる。司会役の伊集院光さんの意表を突いたコメントにハッとさせられる面白い番組だが、何と言っても短い時間でそのキーポイントがつかめるところにその素晴らしさがある。
ここで紹介する『大乗仏教』は6年ほど前に放送されたもので、そのときに視聴したかどうかは覚えていない。200ページ余りの読みやすい長さの本で、青年が疑問を投げかけ、それに講師が答えるという問答形式である。仏教のことを知りたいと思っている読者が、常日頃から疑問に思っていることあるいは新たに生じる疑問をタイミングよく取り上げ、簡潔な説明をしてくれる均整の取れた構成となっている。
それでは内容の説明に移ろう。今日の仏教を大別すると、出家し特別な修行を積んだものだけが悟りに近づくことができる上座部仏教(小乗仏教)と、在家のままでも悟りに近づくことができる大乗仏教がある。大乗仏教は上座部仏教の500年後に誕生したが、上座部仏教もオリジナルな仏教とは異なるので、この本ではオリジナルな仏教を「釈迦の仏教」と呼んでいる。
仏教の開祖である釈迦は「生きることは苦しみである」と捉えた。そして「釈迦の仏教」では、全ての生物は輪廻の世界に住んでいるために苦しみが永遠に続くとし、それから脱するためには、すなわち苦しみから抜け出すためには、二度と生まれ変わることのない世界「涅槃」に到着することだとした。輪廻させているのは「業(ごう)」のエネルギーで、このエネルギーは煩悩によって作り出されるとした。煩悩を消し去るためには、それまでの生活スタイルを離れ、修行だけに特化した生活(出家生活)をすることだとした。要するに「釈迦の仏教」は「自分の力で切り開く」という点に最大の特徴がある。これに対して大乗仏教は後で説明するように「外部の力(超越者・神秘性)」を救いのよりどころとした。
釈迦(ゴーマン・シッダッタ)は、2500年前ごろにインド北部(ネパール)の釈迦族の王子として生まれ、人間は「老いと病と死」の苦しみもだえる生き物であると知り、29歳の時に新たな生き方を求めて出家した。菩提樹の下での瞑想修行により悟りを開き、80歳になるまで弟子とともに各地を回りながら教えを説いた。口伝で次の世代に伝わり、さらに文字を使えるようになると経として伝わるようになった。
紀元前3世紀中ごろ、インド亜大陸の統一をなしたマウリア王朝第三代のアショーカ王が仏教に帰依したことから全土に広まったとされているが、著者の佐々木さんは、仏教が様々な環境で暮らす人々の状況や立場に合わせて選べる「選択肢の多い宗教」に変化したためとみている。アショーカ王の時代に、「部派仏教(釈迦の教えの解釈の違いによって仏教世界が20ほどのグループに分かれた)」という捉え方が成立する。解釈の違いを異端とするのではなく、「釈迦の教えについて違った考え方をしても、同じ領域内に暮らし、布薩(ふさつ:半月ごとの全員参加の反省会)や羯磨(こんま:サンガの事柄を決める会議)をみんなと一緒に行っているかぎり破僧ではない」とした。これによって、仏教の教えの中にはいろいろな解釈があってよい、異なる考えを持つものを否定するのではなく、お互いに仲間として認め合おうという状況が生まれた。
マウリア王朝が滅びるとインドは混乱の時代を迎え、特に北インドのガンダーラ周辺では、さまざまな異民族が流入して乱世の状態になり、出家生活を送れるような状況ではなくなった。このような状況の中で、出家せずとも在家のままで悟りへと近づく方法が探求された。「釈迦の仏教」では修業を積んで阿羅漢(悟りを開いたものが到達する境地で、ブッダよりも下位のレベルに属す)になれるのに対し、大乗仏教では、悟りを開いたときはブッダに成れるとした。「釈迦の仏教」では「現世にブッダは一人しかいない。そのブッダが亡くなると何十億年という長いことブッダの不在期が続く」とされていたのに対し、大乗仏教ではこの世に何人ものブッダが存在するとした。
もう少し具体的に説明すると、輪廻を繰り返すうちにブッダに出会い、そこで誓願をたてブッダから授記され(即ち、ブッダに対してあなたのようになりたいので努力すると誓い、そしてブッダから頑張りなさいと励まされること)、誓願・授記を契機として菩薩となり、輪廻によって何度も生まれ変わり、同時に何人ものブッダに会って励まされ、パワーをもらいながら、利他の気持ちを持って行動することで、最終的にブッダになるというのが、大乗仏教の基本的な考え方である。
それでは大乗仏教の教えを系統別に見ていこう。最初に紹介するのは、「私たちは前世でブッダと会っていて誓いを立てているから、すでに菩薩である」とした般若経である。「釈迦の仏教」では、この世は「天・人・畜生・餓鬼・地獄・(後に阿修羅が加わる)」の五道からなり、生きとし生きる者はこの間を生まれ変わり死に変わることで永遠に繰り返す。出家修行して善行を積めば、阿羅漢として天に生まれ変われるが、しかしここでの生命を終えれば五道のいずれかにまた生まれ変わる。これに対して般若経では、日常生活で善行を積めばブッダと成ることができ、輪廻から逃れられるとした(五道ではなく涅槃の境地)。
「釈迦の仏教」が因果律に基づいて論理的に展開されているのに対し、般若経(紀元前後の成立)は「すでに菩薩にあっている」や「ブッダに成れる」などのような神秘性を帯びている。この考え方を理解するための糸口は「空」である。「釈迦の仏教」ではこの世界をいくつかの方法で分類しているが、その中で五蘊(ごうん)は人間の存在と経験を分析し五つの要素に分けた。それらは色(肉体・木や石などの外界の要素)、受(感受の働き)、想(構想の働き)、行(意思の働き)、識(認識の働き)で、これらが複雑に関係し合いながら寄り集まって定められた因果律に従って刻々と転変し(諸行無常)、世界が形作られていくとした。
石や木を見たとき、我々はそこに実在しているものと考える。しかし釈迦は、実在しているのは目や手がとらえた色や形や感触で、石や木というのはそうした要素を心で組み上げた架空の集合体に過ぎないと考えた。同じように人間も、実体はなく(諸法無我)、確実に存在するのは構成要素だけとなる。これに対して涅槃経では、(石や木に実体がないと見なした考え方をさらに推し進めると)すべての構成要素にもその実体はないと考えられるので、生まれたり消えたり、汚れたり綺麗になったり、増えたり減ったりしているように見えていることもすべて錯覚であるとし、諸行無常さえも否定した。このため因果律はここでは成立しない。行為と結果の関係、すなわち業の因果律(出家修行して善行を重ねれば阿羅漢になれること)すら存在しないこととなる。そこで般若経では、理屈を超えた別の超越的な力によってこの世は動いていて(これにより「釈迦の仏教」が構成した世界観を無化した)、これこそが「空」であるとした。
「空」の理論を理解した人だけが、日常的な善行のエネルギーを全て悟りの方に向けることができるが、その為には六波羅蜜(布施・持戒・忍辱・精進・禅定・智慧)と呼ばれる回向へと向かう修行が必要である。最初の五つは、見返りを求めることなく人と接し、自分を戒める姿勢と慈悲の心を持ち、常に第三者の目で自分を冷静に見つめよと言っている。最後の智慧は、真理を見極めて煩悩を消し、悟りを完成させることと言っている。さらにこれらに加えて、般若経を讃えることをあげている。大乗仏教では、ブッダと会って崇め、供養することがブッダになる近道である。ブッダには簡単に会えないので、経そのものをブッダととらえ、経を讃えることが供養になるとし、さらには書くことも推奨した。このため写経が急速に広まった。
次に説明するのは法華経である。般若経誕生後の50~150年後に北インドで作られたとされる。中国に仏教が伝わったのは紀元1~2世紀とされ、「釈迦の仏教」と大乗仏教の両方が伝わったが、中国で広まったのは大乗仏教であった。中国で法華経を広めることに貢献したのは天台宗の開祖・智顗(ちぎ)で、彼は「法華経が誰でも仏になれる」と強く主張していることに惹かれた。日本には聖徳太子の時代に伝わってきた。しかし広く浸透したのは平安時代で、最澄があらゆる仏教の教えを統合するものとして位置づけた。
法華経の原典はサンスクリット語で書かれ、いくつかの言語に訳されている。漢語訳には三種あり、その中で鳩摩羅什(くまらじゅう)が訳した「妙法蓮華経」が広く流布した。般若経との最大の違いは、法華経が一乗仏という新たな教えを説いたことである。般若経では悟りを開くためには、三つの修行方法(三乗思想)があるとした。それらは、釈迦の教えを聞きながら阿羅漢を目指す「声聞乗(しょうもんじょう)」、孤独な修行をしてたった一人で悟りを開いて他者には説かない「独覚乗(どっかくじょう)」、自らを菩薩と認識し、日常の善行を積むことでブッダを目指す「菩薩乗」である。
一乗仏は菩薩乗と同じではないかという見方もあるが、筆者は三乗思想の一段上にあるものと考えている。般若経では、声聞乗や独覚乗で「釈迦の仏教」における仏道を認めながら菩薩乗で別の道があることを示したのに対し、法華経は「釈迦の仏教」を信じて修行している声聞や独覚に対しても実はすでに菩薩になっていると言い切ってしまっている。このため釈迦の教えとは食い違いが生じている。そこで整合性をつけるために、初転法輪(釈迦が5人の修行者たちに初めて悟りの道を説き、彼らは悟りを開いて阿羅漢になった)を書き換えた。初転法輪では修行者は菩薩でありブッダになれないといっている。そこで初転法輪は方便であって、釈迦は第二の転法輪で真理(誰もがすでに菩薩なのでブッダを目指せる)を説いた。便法を使ったのは、愚かな者を惑わさないためであるとした。
一乗仏での修行方法は、般若経と変わりなく、人間として正しい行いを積み重ねていけばやがてブッダになれるとした。善行の中で大事にしたのは「仏塔供養」、しかしこれは経の前半だけで、後半になると法華経を崇めることとなる。法華経においては般若経よりもさらに経典の存在が絶対的となり、「空」の概念を重視しなくなった。この結果として現世利益にもつながり、経を拝みさえすれば、病気も治るし豊かな生活を送れるようになるとなった。また法難に会うことこそ経の正しさを証明しているとも書かれている。日蓮宗開祖の日蓮が数々の法難に会ったのはそのことによる。嫌がられたり迷惑がられたりすることが、法華経の信者に対する功徳ともなった。そして「経に書かれていることに従っている」という確固とした信念によって、批判や糾弾されることをさほど気にしなくなった。
法華経で一乗仏と並んで重要なのは、「久遠実状(くおんじつじょう)」である。これは釈迦が永遠の過去からブッダとして存在していて、実は死んでおらず、私たちの周りに常に存在しているということを指す。大乗仏教ではブッダを崇めることが最高の善行としていたので、ブッダにいつでも会えるとなると格段にブッダになれるまでのスピードが速まる。江戸時代の学者・富永仲基は、「全ての思想や宗教は前にあったものを超えようとして、それに上乗せして作られた(加上の説)」と言った。法華経での初転法輪の書き換えと釈迦の久遠の存在は、これを表していると言える。
次は少し趣を変えて浄土教である。これは阿弥陀仏がいる極楽浄土へ往生することを解いた教えである。紀元1世紀ごろに成立し、日本に伝わったのは飛鳥時代である。定着するのは法華経と同じように、比叡山延暦寺が開かれた以降で、ルーツは天台浄土教の基本を作った円仁、遊行履歴したと伝えられる空也、『往生要集』を表した源信で、大衆に広めたのは法然と親鸞である。平安時代末期になると、律令制度が崩れ、貴族の力が弱まり、乱世の様相を呈し始める。仏教も同じように堕落し、寺同士がその僧兵によって争うようになる。さらには大凶作や飢饉が起こり住みにくい世の中になると、末法思想(この世に救いはない。現世で悟りを開くのが不可能だ)がはやり始める。最澄が著わしたとされる『末法灯明記』には、永承7年(1052)から末法の時代になったとされている。
そのような中で浄土宗では修行など一切必要ない、「南無阿弥陀仏と唱えさえすれば、誰もが極楽に往生し成仏できる」と説いた。自分で努力しなくても、阿弥陀が救いの手を差し伸べてくれるという他力本願の思想が、多くの信者を得るようになる。般若経や法華経が経を読めと言ったのに対し、南無阿弥陀仏と唱えさえすればよいということになった。また般若経や法華経では過去にブッダに会っているのですでに菩薩であると考えたが、浄土宗ではまだ菩薩になっておらずこれからブッダと出会い菩薩になるとした。すなわち菩薩に会うのを過去ではなく未来とした。
「釈迦の仏教」では、釈迦の入滅後はブッダ不在の時期が続き、56億7千年後に弥勒菩薩が現れて次のブッダに就任するとなっているので、未来に会えるとしても菩薩になるのは簡単ではない。このように時間軸で考えると菩薩になれるのは絶望的だが、浄土宗ではパラレルワールドの概念を新たに創造した。すなわち空間は多世界になっていて、ブッダがいる世界といない世界の二つが存在し、ブッダのいる世界を「仏国土」と呼んだ。死んだ後すぐに仏国土に生まれ変われれば、ブッダと出会い菩薩修行ができるようになるとした。さらに仏国土には修行に適した世界とそうでない世界が存在し(それぞれの仏国土には一人のブッダが存在)、その中で理想的な仏国土は、他の仏国土に自由に行き来できる極楽浄土(ここにいればたくさんのブッダに会いに行くことができ、より速くブッダに成れる)で、ここのブッダは阿弥陀であるとした。
釈迦の仏国土の方が、阿弥陀の仏国土よりもよさそうに思われるがそうではない。釈迦は「あなたのようなブッダに成りたいので努力します」と誓いを立てたのに対し、阿弥陀は同じことを言った後、48の願掛けをし、そして「ブッダに成るための修行を終えたあとでも、私の仏国土がどこよりも素晴らしいものになるまでは、私はブッダに成りません」と誓った。阿弥陀は、自分の悟りだけでなく、願掛けで全ての生き物の成仏を願った。浄土教での釈迦は、阿弥陀という偉い方がおられる素晴らしい世界があるということを伝えるという役回りである。
法然は、極楽浄土に行くためには往生したいと願い念仏を唱えることが大切と説いたのに対し、親鸞は願わなくとも阿弥陀の方から手を差しのべてくれるのだから、感謝のために唱えればよいと説いた。これによって念仏を唱える目的が、悟り(涅槃に至ること)から救われること(楽しくてきらびやかな生活で不自由のない生活を永遠に続けること)へと変わった。
今度はさらに趣を変えて華厳経と密教である。華厳経を象徴するのが奈良の大仏の廬舎那仏坐像である。華厳経はサンスクリット語で「ブッダアヴァタンサカ・スートラ」だが、これは「無数のブッダの壮麗なる集まり」を意味する。日本に宗旨が伝わったのは8世紀半ばで、金鐘寺(こんしゅじ:東大寺の前身)の良弁(ろうべん)が、新羅で学んだとされる審祥(しんじょう)を招いて、『華厳経』の講義をしてもらったのがきっかけとされている。華厳経は奈良時代には国家仏教として重視されたものの、その後はパッとしない。しかし日本人のものの見方に大きな影響を与えた経である。華厳経では「死ななくとも、この世界で生きたままブッダに会うことができる」と説いた。それを可能にしたアイデアは「別の世界にいるブッダが移動できないのなら、ブッダが自らの映像を私たちの世界に送ってくれればよい」である。そして「バーチャルはリアルである」とした。
華厳経では宇宙には様々なブッダが存在するが、それらは「毘廬舎那仏(びるしゃなぶつ)」という一人のブッダにすべて収束されるとした。これはインターネットの世界に例えると理解しやすい。インターネットにはネットワークの中心というものがなくネットワーク全体が一つの存在である。これが毘盧遮那仏である。各世界のブッダは毘盧遮那仏というネット本体の先にそれぞれ存在していて、それぞれのブッダからまた別の世界のブッダが放射状につながり、無限のブッダ世界が宇宙に広がっている。一見、個々のブッダ世界は孤立しているように見えるが、全てのブッダは毘盧遮那仏とつながり、毘盧遮那仏は個として存在するばかりではなく、全てのネットワークを覆いつくす巨大な存在でもある。華厳経では、これを「一即多・多即一」という表現を使って表している。これは自己相似性という性質を持つフラクタルの概念に似ている。
華厳経での「ネットワーク本体としての毘盧遮那仏がいて、それがそれぞれの世界へメッセージを送っている」という中央集権的な思想が、奈良時代の朝廷が望んでいた中央集権的国家体制の構造と同じだったためにこの時代に重宝されたが、平安時代や鎌倉時代になると人を救うことを目的とした宗教に変化していくので、救いや悟りの方法が示されていない華厳経はその存在価値を失ったと見られている。
密教は華厳経に似ている。密教での最重要仏は大日如来、サンスクリット語では「マハーヴァイローチャナ」で、これは毘盧遮那仏と同じスペルである。インドで密教が誕生したのは4~5世紀で、ヒンドゥー教の勢力が強まり仏教が衰えていく中で、生き残る方法を考えた大乗仏教が、ヒンドゥー教やバラモン教の呪術的な要素を取り入れて誕生させたのが密教とされている。主要経典ができ体系化されたのは7世紀ごろである。密教を最初に日本に持ち帰ったのは最澄(天台密教:台密)、そしてキーマンは空海(真言密教:東密)である。密教は顕教と対比される。顕教は釈迦が秘密にすることなくすべての衆生に向かって説いた教えで、密教は大日如来が秘密のものとして修行の進んだ人にだけ教えたものである。
根本経典は『大日経』と『金剛頂経』で、唐の僧侶・恵果がこれらを統合して真言密教のベースを作り、それを受け継いだのが空海の真言宗である。初期の頃は現世利益を成就する呪文を唱えたり、呪術的な儀式を行ったりしたが、中期の頃は華厳経の毘盧遮那仏と合わさりながら、組織的な仏教教義を確立した。空海は「大日如来は宇宙そのものであるとともに、微塵の一つ一つが大日如来である」と説いている。従って華厳経のフラクタルな世界観を引き継いでいるといえる。「曼荼羅」はその例と見てよい。
華厳経には具体的な修行方法は示されていなかったが、密教では、修行のゴールは「即身成仏(生きたまま仏の境地に至る)」で、そのためには「三密加持の行」が基本になると説いている(なお、ミイラは即身仏、ちょっと紛らわしい)。三密とは身密(印を手で結ぶ)・口密(真言を唱える)・意密(宇宙の真理を心に描く)で、これは「今ある私が仏である」ことに気づき実感するための神秘的な特殊儀礼である。既にブッダのいる宇宙の中に私たちが生きているのだから、それに気がつけば誰でもブッダに成れるというのが密教の悟りである。そして悟りの問題を解決したことで、密教は現生利益を第一に考える実利的な仏教へと向かっていった。
少し横道に逸れて、仏教がインドでなぜ衰退したかの話を簡単にする。仏教もヒンドゥー教も輪廻転生についての概念や、悟りを開いて輪廻を止めるという考え方は一緒である。ヒンドゥー教では、宇宙を貫く根本原理として「ブラフマン(梵)」というものがあり、我々個人には個体原理「アートマン(永遠不変の自我)」が存在していて、この二つが一体化したとき悟りに至ると説いている。これとは逆に仏教は、永遠不変の自我ではなく、諸行無常で無我、すなわち自我があるという思いを消滅させる修行へと向かった。しかし「釈迦の仏教」から大乗仏教へと変容することで、ヒンドゥー教にどんどん近づいた。華厳経や密教では「この宇宙全体が一つのブッダの世界であり、そこに私たちは生きている」とすることで、ヒンドゥー教の「梵我一如」とほぼ同じになり、インドでは仏教はヒンドゥー教に取り込まれてしまった。
次に紹介する涅槃経はさらにヒンドゥー教に近づいて「もともと私たちの内部にブッダは存在し、私とブッダは常に一体である」という世界観である。「皆さんは誰もが仏であり、生まれながらにして仏性(ぶっしょう)を有している」とお坊さんから言われた経験を持っている人は多いことだろう。ここで仏性は「ブッダとしての本性・性質」を表す。仏性という言葉は大乗仏教になって初めて使われ、初めて説いたのは涅槃経である。
紛らわしいのだが涅槃経には、紀元前の「釈迦の仏教」のものと、4世紀ごろに書かれた大乗仏教のものとがあり、前者は阿含「涅槃経」、後者は大乗「涅槃経」という。阿含涅槃経では「自分で努力して悟りの道を歩め」とするのに対し、大乗涅槃経では「ブッダとは、無限の過去から無限の未来へと変わることなく存続する永遠の存在である」とする。大乗涅槃経では、釈迦が入滅したのは方便で、本当は死んでいないことになっている(如来常住:法華経での久遠実成とほぼ同じで、大乗仏教の教えに共通する考え方)。
大乗涅槃経でもう一つ大事な考え方は、「一切衆生悉有仏性(いっさいしゅじょうしつうぶっしょう)」である。全ての生きとし生きるものには仏性があるとするもので、生きとし生きるものには、インドでは植物を含んでいなかったが、中国では植物まで含むようになり、日本では無機物さえも含むようになった。これは日本に古くからあるアミニズムの世界と結びついたともいえる。
大乗涅槃経の「一切衆生悉有仏性」の考え方と関係が深い「禅思想」について紹介する。禅は中国発祥の思想で、道教などをベースとし、「釈迦の仏教」の修行の一つである「禅定(瞑想によって心を集中する修行)」と結びついたのが起源である(開祖は5世紀後半南インドから中国に来た達磨)。鎌倉時代に中国に渡った栄西と道元が、臨済宗と曹洞宗を開いた。これが禅宗のはじまりである。禅では「私たちの内側には仏性があり、それに気がつくことが悟りへの道である」と捉え、仏性に気がつくための修行方法として座禅修行を重視した。自分の中の仏性に気がつくとは「主観と客観、自己と世界が分かれる以前の存在そのものに立ち戻る」ことである。
臨済宗は室町幕府の庇護を受け武士や公家の間に広まり、曹洞宗は地方の豪族や農民を中心に広まっていった。織田信長は仏教を迫害したが、臨済宗は保護され武士たちの心のよりどころとなった。江戸時代になると、中国から黄檗宗(おうばくしゅう:禅宗の一派)が入ってきた。堕落しつつあった日本の禅宗は危機感を覚え、臨済宗からは黄檗宗批判、曹洞宗からは道元への復古運動がおこる。江戸時代の禅宗復興のキーマンは白隠慧鶴(はくいんえかく)で、「衆生本来仏なり」と分かりやすい言葉で、大衆の心をつかむことに成功した。
本の紹介が長くなったので、最後にまとめることにしよう。このテキストを読んでまず驚かされたのが、その多様性である。「釈迦の仏教」の根幹は、我々が生きているところは輪廻の世界で、あらゆる苦しみに満ちている。この苦しみから脱するためには悟りを開くことで、これによって輪廻の世界から解脱し涅槃に至るとされている。これまでに説明してきたように、解脱の方法を時代の要請に合わせてかくもたくさん用意したのかと脱帽である。
解脱するためには、上座部仏教では出家して修行に没頭するとなっているのに対し、大乗仏教では出家しなくても良いとしている。「釈迦の仏教」と上座部仏教が、因果律に基づいて教義が展開されるため論理的であるのに対し、大乗仏教の方は因果律を超えた神秘性が導入され、悟りを開く方法にいくつもの工夫がなされた。
最初に示されている方法は、般若経や法華経に見られる時間軸の短縮で、悟りを開くためにはブッダに会わなければならないが、生まれる前に既に会っているので、経を読んだり写したりしてブッダを崇めなさいとする。しかしこの方法では既に前世でブッダに会っていなければならない。末法思想では、釈迦が亡くなったあと次のブッダが現れるまでには絶望的に長い時間がかかるとされた。そこで次に導入されたのが死後にブッダに会うことができるという考え方で、世界はいくつもあり、その中にはブッダが住んでいる世界があり、死後にそこへワープできるとした。とりわけ阿弥陀が住んでいる世界は、浄土と呼ばれ極楽天国である。生きている間に念仏を唱えればよいとする他力本願の浄土教が現れ、悟りから救いへと大きく変容した。
次は三つ目の方法である。四国の遍路さんは外国人にも人気があり、「同行二人(どうぎょうににん)」という白衣を身に着けたカップルを見るとほほえましくなるが、もちろんこれはパートナーと二人でお遍路さんをしているという意味ではなく、弘法大師が一緒についていることを表している。弘法大師・空海が広めた密教は曼荼羅に象徴されるように、大きく切り取っても小さくてもブッダがいる世界である。数学でのフラクタルに似ていて、ブッダ(大日如来)がどこでも傍にいる世界である。これによりブッダといつでも会えるので、悟りを開くスピードが格段に速められただけでなく、現世利益を第一に考える実利的な宗教となった。これと似ていたのが奈良時代の華厳経で、その毘盧遮那仏と大日如来は、サンスクリット語では同じスペルである。
最後の方法は中国発祥の禅宗で、「自身の中に仏性がある」とすることで、ブッダとの距離は縮まるどころか無くなってしまった。異なる教義を受容しながら多様性を生み出してきた仏教の柔らかな復元力に感心させられた一方で、誕生国のインドでは廃れ、中興した中国では限定的になったのに対し、日本では墓参り・葬儀などでの日常に組み込まれているこの相違はどこに起因しているのだろうと新たな疑問が湧いた。