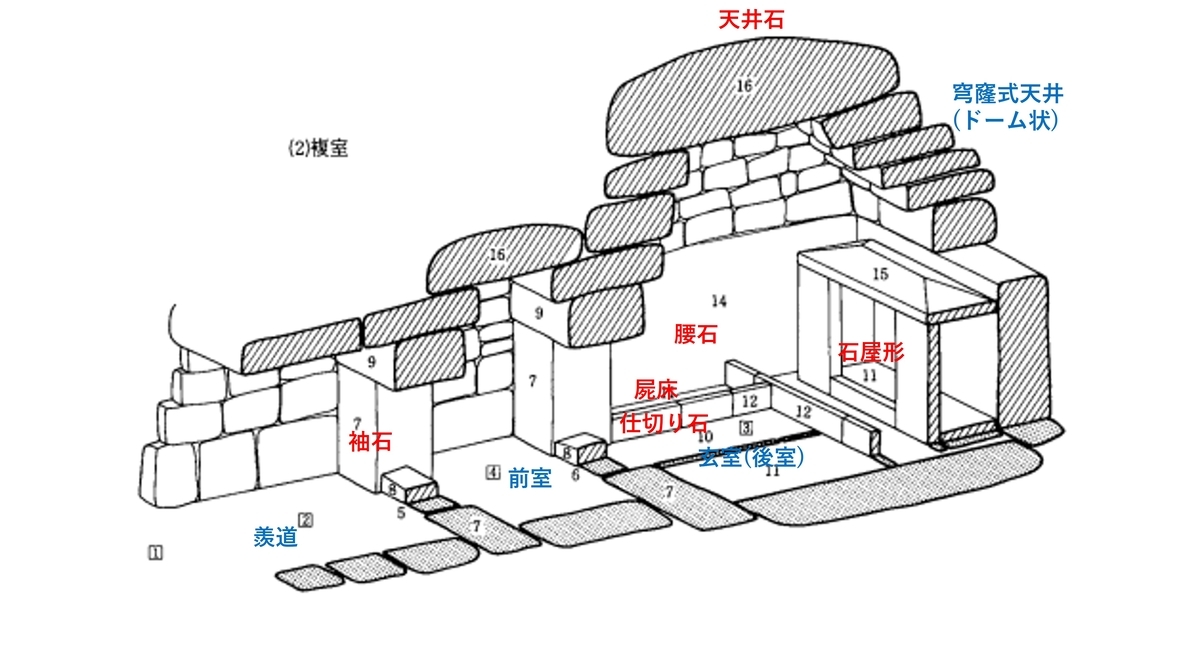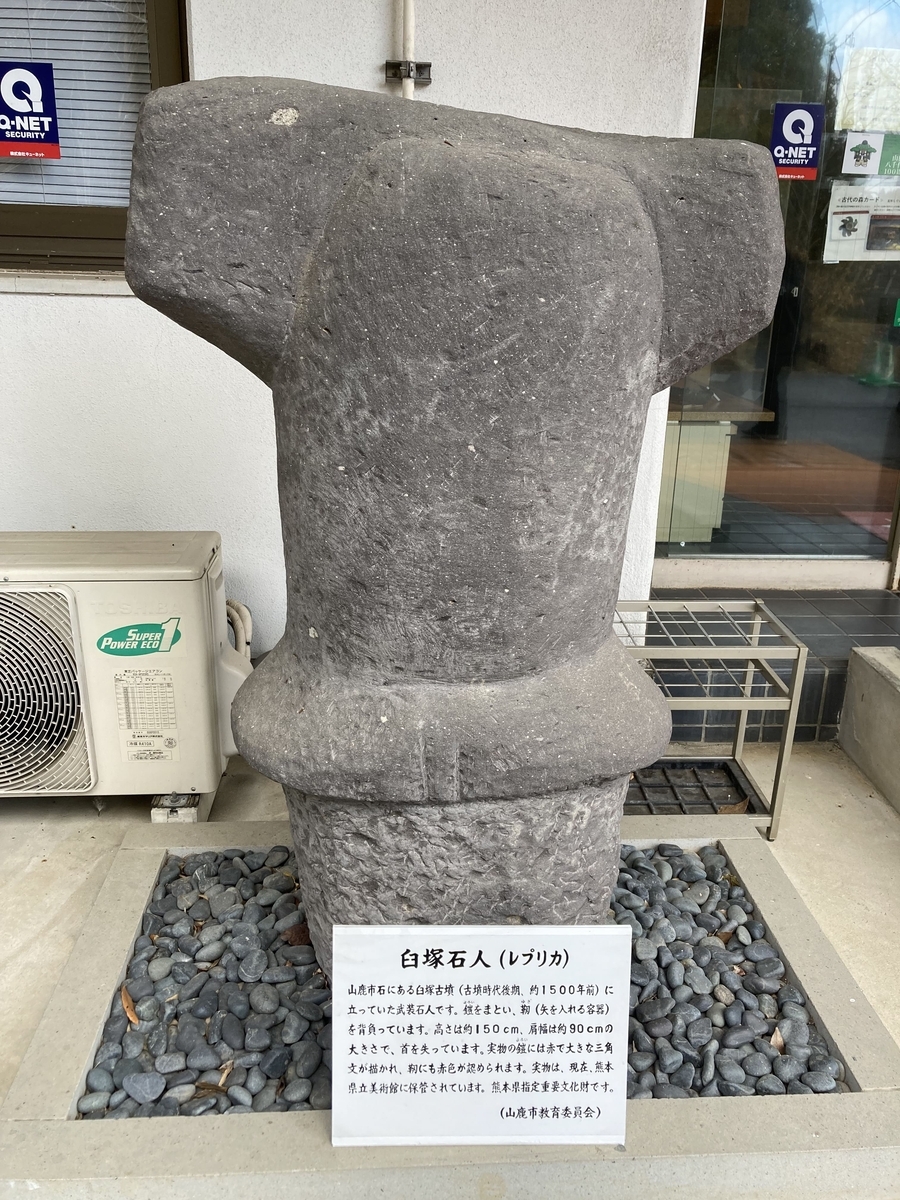なんとも古めかしく、それでいて刺激的なタイトルの本だろう。かつては「封建的なオヤジ」という言葉もあったが、今はそれも死語になってしまった。封建的といわれても、それがどういうものであるかを感覚的に知っている人は少なくなってしまった。
日本の社会体制が封建制であったのは、平安時代後期から明治維新までであろう。その基盤となったのは、鎌倉時代の御恩と奉公の関係である。将軍は御家人(家臣)に対して、荘園(土地)を管理(支配)する職(地頭)に任じ、その代償として、御家人は軍事的に奉仕しなければならないという主従関係が築かれていた。荘園の耕作を実際に行うのは百姓(農民)で、年貢を納めるだけでなく夫役(労役)も課せられた。そして、御家人と百姓との間には大きな所得格差があった。
近代国家になって中間層が出現し、高所得者と低所得者の間は、これら中間層の人々で埋められ、中間層に属する人々の割合も急激に増えた。日本では、一億総中流といったこともあった。そして、20世紀後半にソ連が崩壊し冷戦が終了したとき、多くの人がこれからは民主主義を享受できるようになると楽観的に考えた。しかし、グローバリゼーションの進展とともに、所得格差が目立ち始めた。
21世紀になると格差が極端に拡大していると指摘されるようになるが、それらの中で、セルビアの経済学者のブランコ・ミラノヴィッチさんが2012年に発表した「エレファント・カーブ」は衝撃的であった(図は総務省の令和元年版「情報通信白書」のポイントからである)。新興国ではその経済発展によって中間層の伸びが著しいのに対し、先進国では製造業の移転によって中間層が壊滅し、IT・金融分野の成長によって信じられないような富を有する層(富裕層)が出現した。

この本によると、1945年から1973年にかけて、アメリカの上位1%は、米国国民全体の所得の4.9%に過ぎなかった。それが現在は、アメリカの最富裕層400人の富の合計は、下位1億8500万人の富の合計を上回っている(なお、アメリカの総人口は3億4千万人である)。この傾向は欧米だけでなく、社会主義国を自任している中国でも同じである。
「エレファント・カーブ」は中流階級が消滅していることを示すが、本ではこれによって過去にどのようなことが生じたかを説明してくれる。古代アテネやローマの初期の民主主義は、強い発言力を持ち、財産を所有する中流階級に支えられていた。アリストテレスは、経済と国家を共に支配する寡頭制の危機に警鐘を鳴らした。実際、富の集中が進むにつれ、古代ギリシャの民主制や市民主体の共和政ローマは弱体化した。共和政末期になると、全財産の75%以上を人口の約3%が所有し、5分の4以上の人々は財産を所有しなかった。
経済格差は所得の面からとらえた一面であるが、それでは現在の社会はどのような構造になっているのであろうか。著者は次のように述べている。ヨーロッパの封建時代には、エリート聖職者と貴族が権力を分け合っていたが、現在の新しい封建制の中核には、有識者層と寡頭支配者層の連鎖関係があるとしている。二つの階級は、ニューヨーク、サンフランシスコ、ロンドンなどの都市において同じ学校に通い、同じような地区に住んでいる。そして、彼らは共通の世界観を持ち、大概の問題で協力するが、中世の貴族と聖職者の間に見られたように対立することもある。しかし、グローバリズム、コスモポリタンニズム、学歴や資格の価値、専門家の権威については、間違いなく同じ見解を有している。
そして、権力連鎖を可能にしているのはテクノロジーである。テクノロジーはかつては草の根の民主主義や意思決定に役立つと期待されていたが、今や監視や権力強化の道具となっている。ブログの普及で情報民主主義の様相を呈しているものの、情報の流れや文化のあり方はアメリカ西海岸に拠点を置く少数の企業が厳しくコントロールしている。現在の新しい大領主は、鎖帷子(くさりかたびら)やシルクハット姿ではなく、ジーンズやパーカーを着込んで未来を導く。技術者エリートは科学的専門知識に立脚した「新しい権力の司祭たち」の21世紀版である。
革命前のフランスはアンシャンレジームと呼ばれる身分制で、第一身分は聖職者、第二身分は貴族で、第三身分は聖職者にも貴族にもなれない平民であった。封建制になりつつある今日の社会では、有識者が第一身分で、寡頭支配者が第二身分で、第三身分は二つの異なる集団から成り立っていると筆者はみている。
第一の集団は土地持ちの中流階級でイングランドのヨーマン(独立自営農民)と似ていて、同じような独立精神を都市・郊外の文脈に持ち込んだ人々である。かつてのヨーマンは封建秩序を覆すのに重要な役割を演じたが、現代のヨーマンは寡頭支配者の下で逆に苦しめられている。
第二の集団は労働者階級で、中世の農奴のようになりつつあり、土地、建物などの重要な資産を所有する機会や、政府から受け取る給付金以外で自分の境遇を改善する機会を、失いつつある人たちである。現代の日本社会で見ると、前者は給与所得者、後者はパートやアルバイトで生活している人々となる。ロストジェネレーションと呼ばれる就職氷河期時代の人々は、ヨーマンの没落を典型的に表している例と言える。
第一身分は、聖職者から有識者へと変わったが、宗教の推進者であることには変わりはない。その典型は環境保護主義で、グリーン教と言っても良い、今日の時代の新しい宗教になりつつある。中世のカトリック信仰と同じように、グリーン教では人間の活動に起因する破滅の到来を予測している。グリーン教が中世の宗教と変わりない点は、貧しさを甘んじて受けるように他人に輸したり、貧しさを美徳として称賛する人々の中には偽善的な人がいることである。これについては、後でもう少し詳しく述べる。
本の中をすべて紹介することはできないので、特に興味を引いたところをいくつか紹介しよう。
最初は、アメリカをはじめとする先進国の間で、有識者と一般人の間での分断が大きくなり始めていることの典型的な例を示すものである。今年は4月に夏日を迎えるような気象変動に見舞われ、多くの人が何とかしないと大変なことになると思った。しかし、環境保護の推進者(先に述べたグリーン教の聖職者)は、贅沢な生活をしながらの口先だけの信頼できない人々だと指摘している箇所である。
中世においては、大半の司祭と信者は厳しい窮乏状態になったが、多くの司教は贅沢に暮らしていた。これと同じようなことが起きている。グリーン・リッチ(環境成金)と呼ばれる連中は、他人には消費を控えるように呼びかけながら、自分たちは炭素クレジットを購入したりして現代版の贖宥状を買っている。2019年の地球環境会議に出席する人々を乗せたおよそ1500基のプライベートジェットは温室効果ガスをまき散らしながらダボスに到着した。このように主張とは全く反対の行動をしている有識者はいづれ激しい反発にあうと予想しているがどうだろう。
その次は、Anywhere族(どこでも行ける人々)とSomewhere族(どこかにいる人々)である。イギリスのジャーナリスト・デイヴィッド・グッドハートが『The Road to Somewhere』で提唱した概念で、現代社会におけるる文化的対立を指摘したものである。Anywhere族は、高い教育水準を持ち、グローバルな視点で物事を考え、移動性が高く、どこでも生活できる能力を持ち、個人主義的でリベラルな価値観を支持する傾向の人々である。これに対してSomewhere族は、地域やコミュニティに深い愛着を持ち、伝統や安定を重視する人々で、移動性が低く、地域にとどまる傾向があり、保守的な価値観を支持する人々である。Anywhere族とSomewhere族の対立は、イギリスではEUの離脱をめぐる分断を、アメリカではグローバリゼーション・国境政策をめぐる分裂を招いた。これらは有識者とヨーマン・労働者階級の激しい対立を示すもので、その解決は困難を極めそうである。
最後は本当に信じてよいのか疑うが、新しい封建制から逃れられるのはもしかすると日本と論じている部分である。日本は、たとえ経済の成長が止まっても、その代わりに精神的なものや生活の質の問題に関心を向けられる高所得国のモデルとなっていると考える学者もいる。日本は将来世界を征服するようなことはないであろうが、高齢化が急速に進む一方で快適な暮らしが送れる、アジアにおけるスイスのような存在になりうると考えている専門家もいる、となっている。このようになって欲しいと心から望むが、果たしてどうであろう。
一昨日、カリフォルニア州が日本をGDPで抜いたという記事があった。カリフォルニア州は、面積では日本より少し大きく、人口では1/3程度である。カリフォルニア州はアメリカンドリームを実現できる素晴らしい地域と思われている、あるいは、これからの文脈ではかつては思われていた。サンフランシスコの近くには、世界のIT産業を牽引してきたシリコンバレーがある。かつては金を目指してカリフォルニアを目指してきたが、20世紀後半には、IT分野で一旗揚げようと世界中から若者がこの地に群がってきた。その頃のシリコンバレーは、活気と夢が溢れるユートピアであった。しかし、そのような状況もつかの間、少数の者だけが成功し、テックオリガルヒと呼ばれる極めて少数の超富裕層が台頭した。IT企業は、たくさんの雇用を生み出す製造業ではなく、少数の優秀な技術者によって支えられるソフトウェア産業であるため、雇用は増えず、多くの人はギグワークで糊口を凌ぐこととなった。その結果、シリコンバレーは、最も富んでいる人々が、そして、最も貧しい人々が生活しているところで、新しい封建制の最先端であると著者は述べている。このような現実を知ると、一昨日のニュースは喜べない。そして、何とも言えない恐ろしいデストピアを感じたのだが、私だけだろうか。日本がこのようにならないことを願ってこの本を閉じた。